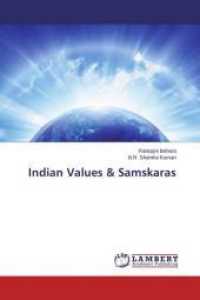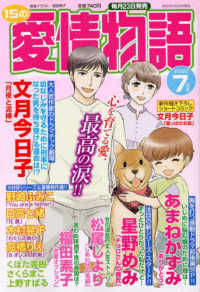内容説明
言語を介して人間存在の本質に迫る試みは決して新しいものではない。だが、デリダからスーフィーをへて空海へ、ソシュール言語学からイスラーム神秘哲学をへて唯識・華厳の学へと、この広大な精神世界の体験を言語化しようと企てたものはいまだかつてなかった。古今東西の思想を自由闊達に渉猟し、しなやかな精神をもって「意味の深みへ」と向かう碩学の思索は、思想のポストモダン的状況において、知の沃野が東洋哲学の世界を通して限りなく拡がることを啓示する。
目次
1(人間存在の現代的状況と東洋哲学;文化と言語アラヤ識―異文化間対話の可能性をめぐって)
2(デリダのなかの「ユダヤ人」;「書く」―デリダのエクリチュール論に因んで)
3(シーア派イスラーム―シーア的殉教者意識の由来とその演劇性;スーフィズムと言語哲学;意味分節理論と空海―真言密教の言語哲学的可能性を探る;渾沌―無と有のあいだ)
著者等紹介
井筒俊彦[イズツトシヒコ]
1914‐1993年。1937年慶應義塾大学文学部卒業。1968年まで慶應義塾大学文学部教授。以後、マッギル大学(カナダ)教授、イラン王立哲学アカデミー教授、Institut International de Philosophie会員を歴任。専攻は言語哲学・イスラーム哲学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
寛生
54
【図書館】衝撃的な書物。信じられないくらい凄い本。「世界がまるで違った様相を示し始める」読了感。(257)井筒の手によって僕の全体が持ち上げられ、逆さまにされて、2、3回揺さぶられたような感覚。聞こえない声、「声なき声」が砂漠を彷徨う私を吹き抜けていく。意識せずともすべての経験が私という存在の深みの痕跡となる。「心の下意識的領域に場を持つ意味の生成過程、深層意識の薄暗がりの中で点滅し、活動している無数の意味可能体まで掘りさげてコトバというものを」(206)徹底して考えよ!という井筒の命令の声が響く。2014/05/09
非日常口
17
グローバル化とは浸食度なのか。コミュニティが
孤立的に散在したときは、世界は途方もなく広かった。が、BMIなど個が世界と繋がる今、余白は失せ
狭苦しく、アジール的な逃げ場もない。ネットワーキングは古来よりあった思想だ
が、資本の欲望が技術を追いつかせた。そこで氾濫するエクリチュールは言語の規制性を個に寄生させアナロジーを削りだしている。言語の獄屋を広げるだけのシェアではなく、自己にコトバを薫習し、アーラヤ識にある種子に世阿弥の言う花を咲かせる時を持ち、流動性を取り戻そう。境界は越えるのでなく動かすものだ。2014/10/28
みぎ・妖子
2
意識と本質より分かりやすい。こっちを先に読むのもいいかも。やっぱり素晴らしい。特に、1.2.5.6.章はじっくり読んだ。2009/05/17