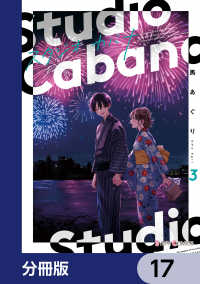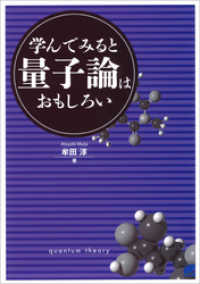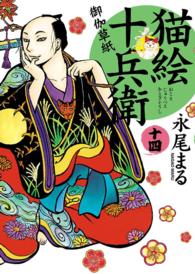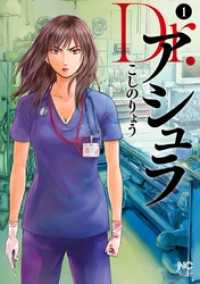内容説明
倭国の女王卑弥呼は二世紀末に登場する。「魏志倭人伝」によると女王の統治下には三〇余国があり、特色ある地域文化が栄えていた。王位はその後、男帝をへて宋女の壱与が継ぎ、三世紀末に及んだという。謎が多く、遺跡発掘などで新資料が見つかるたびに論争が活発化する邪馬台国の実相を、卑弥呼が生きた時代に軸足を置いて、考古学研究の成果から探っていく。朝日カルチャーセンターで人気を博した特別講座を出版化した待望の一冊。
目次
第1章 卑弥呼以前の倭―「倭国大乱」の実態(中国史書にみえる倭と「倭国乱」;卑弥呼共立の前提となった「倭国乱」 ほか)
第2章 卑弥呼登場―卑弥呼を「共立」したクニグニ(卑弥呼の登場した時期;「倭」の地域とは ほか)
第3章 卑弥呼と男弟―三世紀にヒメ・ヒコ体制はあったか(仙台平野の庄内式土器;おおやまと古墳集団の分布調査 ほか)
第4章 卑弥呼の鬼道と壷形の宇宙(鬼道のちから;神仙思想の伝来 ほか)
第5章 「棺ありて槨なし」―墳墓からみた邪馬台国(二~三世紀の棺槨;仮説・竪穴式石室の成立過程)
著者等紹介
石野博信[イシノヒロノブ]
昭和8年宮城県に生まれる。昭和31年関西学院大学文学部卒業。昭和36年関西大学大学院文学研究科修了。昭和41年兵庫県教育委員会嘱託、技師。昭和46年~平成2年3月奈良県立橿原考古学研究所技師、調査課長、研究部長、副所長兼附属博物館館長。平成3年4月より徳島文理大学教授、奈良県香芝市二上山博物館館長、現在に至る。文学博士
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。