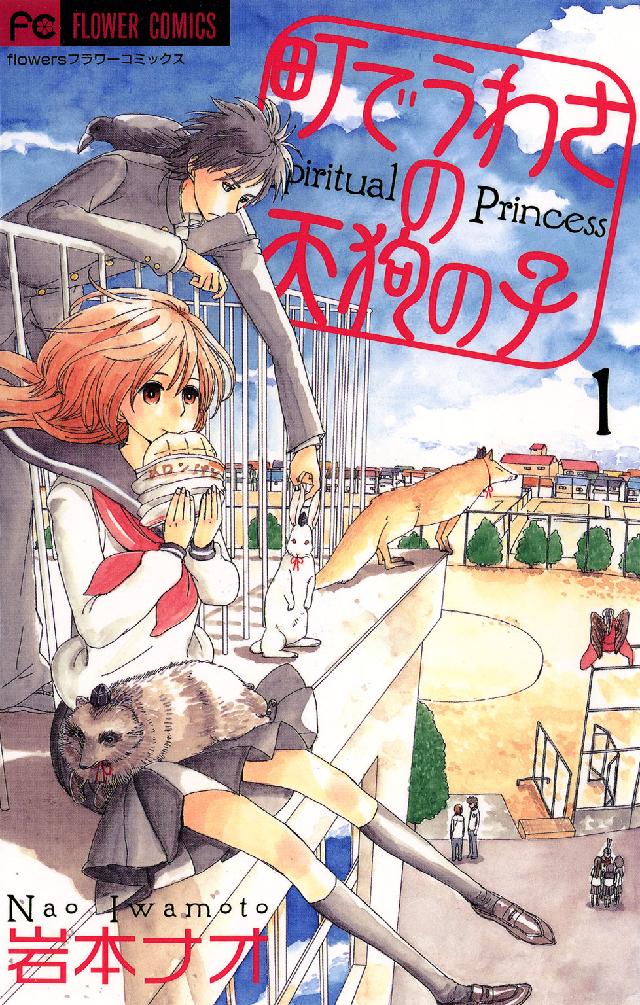内容説明
イエスはどんな言葉で、弟子や民衆と語り合ったのか。聖書の読者が抱くこの素朴な問いに答えを与えるべく、新約時代のパレスチナにおける言語状況を諸資料から掘り起こし考究した記念碑的著作!
目次
1 イエス時代の言語状況(ギリシア語;ヘブル語;アラム語)
2 イエスと聖書翻訳タルグム(タルグムとは;死海文書中のタルグム;イエスとタルグム;イエスとアラム語)
付論1 メシア告白の問題(文法的検討;テキストの解釈;古代教会の解釈;ラビ文献の検討)
付論2 “エッセイ”新約聖書本文批評学などについて(マルコ一41;マルコ一六章;ヨハネ一18b;ヨハネ七53-八11;ヘブル一3;ヘブル二9;1ヨハネ五7-8;マタイ一〇29)
著者等紹介
土岐健治[トキケンジ]
1945年名古屋市生まれ。東京神学大学卒業。東京大学大学院西洋古典学専門課程博士課程修了。現在、一橋大学名誉教授
村岡崇光[ムラオカタカミツ]
1938年広島市生まれ。東京教育大学(現筑波大学)英文科卒業。同大学大学院言語学科博士課程中退。エルサレムのヘブライ大学にて博士号(Ph.D.)取得。英国マンチェスター大学講師、オーストラリアのメルボルン大学教授を経て、1991年オランダのライデン大学ヘブライ語教授に就任、2003年に定年退職。現在、同大学名誉教授。エルサレムのヘブライ語アカデミー名誉会員。ライデン郊外ウーフストヘースト在住(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Timothy
8
イエスが普段触れていた律法は何語だったのか、という疑問から手に取った本。残念ながら結論は出なかったが、ギリシア語は当時地方の一般的なユダヤ人にも広く使われていたこと(イエスが話したかは不明)、長年書き言葉・学者の言語とされてきたヘブル語だが後の研究で口語としても生きていたことが分かっていること、イエスらがタルグム(アラム語訳された旧約文献)に触れた可能性はあることなどが分かった。知りたかったこととは違うが、「メシアなのか」と問われたイエスの"σύ λέγεις/ειπας."についての考察も面白かった。2021/08/11
takao
1
ふむ2021/09/15
-
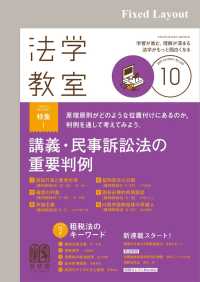
- 電子書籍
- 法学教室2019年10月号 法学教室
-
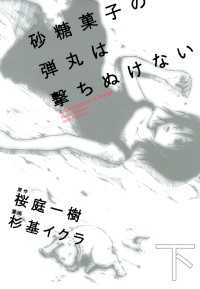
- 電子書籍
- 砂糖菓子の弾丸は撃ちぬけない(下) A…