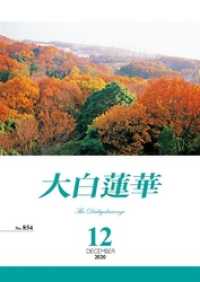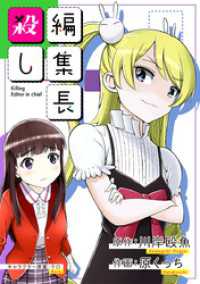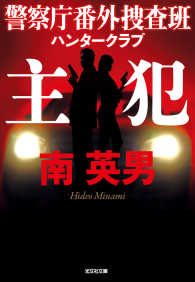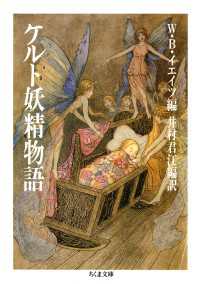内容説明
見れども飽かぬ風景、人を勇気づける風景、時代を超えて人々に愛され続ける風景…土木、建築、都市のあらたなデザインの地平を拓き、次代のよりどころとなる風景を手にするために、今われわれがすべきことは何か。風景を想うすべての人たちに、デザインの最前線から呼びかける、力強いメッセージ。
目次
1 LandscapeからGroundscapeへ(土木・建築・都市の領域を越えて)
2 土木・建築・都市―デザインの戦場(土から商、骨から皮、海から島へ;人と時と土地へ仕掛ける ほか)
3 グラウンドスケープデザイン最前線(朧大橋;勝山橋 ほか)
4 風景の再構築のために―村社会を脱して(連帯の戦線へ)
著者等紹介
内藤広[ナイトウヒロシ]
東京大学教授(工学系研究科社会基盤学専攻)。1950神奈川県生まれ。1976早稲田大学大学院理工学研究科建設工学専攻修士課程修了。1976フェルナンド・イゲーラス建築設計事務所。1979菊竹清訓建築設計事務所。1981内藤広建築設計事務所。2001東京大学助教授(工学系研究科社会基盤学専攻)。2002同教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ja^2
3
土木・建築・都市の各職能の融合が、私の司る組織に与えられたテーマである。司馬遼太郎は、「文化とは特定の集団においてのみ通用する非合理でかつ偏ったもの」と言ったが、まさに土木・建築・都市にはそれぞれの文化があり、彼らの融合は思いの外難しい。▼そうした中、内藤廣氏の著作はいつもに大きな示唆を与えてくれる。本書もまたしかりで、各職能のコラボのあり方は参考になった。▼だが私の目指すのは、コラボではなく融合なのだ。コラボは足し算、融合してこそ掛け算になるというのが私の持論である。言葉遊びではないことを証明したい。 2015/08/30
おこ
0
前の時代・世代のアンチテーゼとして次の主義思想が生まれてくる。前後の文脈が途切れてしまったものをそれも歴史的背景の一部として捉えて、現代のまちに残し、反映させていこうという取り組みが大切。細分化された分野がある中で、そこを横断していく働き方が今後を生き残っていく上で欠かせない。他の意見を受け入れ、それを丸呑みするのではなく、自分の中の変化に繋げていく。様々な専門家が集まったデザインチームで都市・土木・建築・造園などを総体として作り上げていく手法はとても面白そうだ。2018/03/18