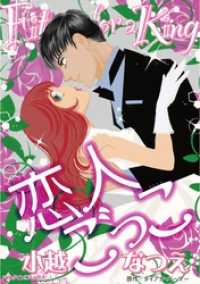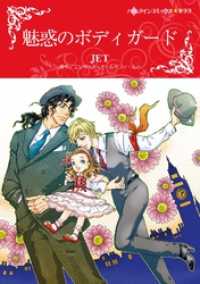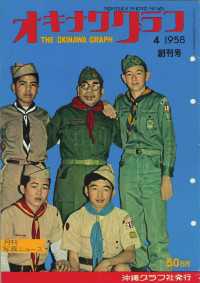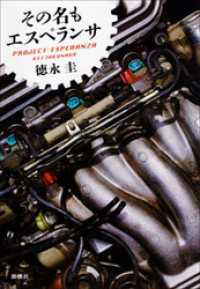内容説明
相次ぐ巨大スタジアムの建設、新球団を生んだプロ野球界の再編など、スポーツと都市、スタジアムと市民のかかわりが大きな転換点にさしかかっている。正力松太郎はなぜ自前の球場を持たなかったか?昭和天皇の相撲観戦にはいかなる意味があったのか?財界の名物男、永田雅一が描いた夢の球場とは?スタジアムが戦後史の中で果たしてきた役割、映し出してきた時代の空気を探る。
目次
第1章 後楽園球場―稀代の興行師、正力松太郎の呪縛(砲兵工廠跡地に建てられた待望の球場;自前の球場を持たなかった正力松太郎 ほか)
第2章 両国国技館―相撲界の悲願と昭和天皇の祈り(風船爆弾の製造工場;「占領軍慰安大相撲」と横綱双葉山の引退 ほか)
第3章 川崎球場―高度成長を支えた労働者の「遊園地」(「三つのスタジアム」が密集する都市;若い労働者の町 ほか)
第4章 日本武道館―「国粋」と「国際」の間(伝統と国際化の相克;超党派「武道会館建設議員連盟」 ほか)
第5章 東京スタジアム―「ラッパ」と呼ばれた男、永田雅一の栄光と挫折(ラッパと呼ばれた財界の名物男;不運つづきの球団オーナー ほか)
著者等紹介
阿部珠樹[アベタマキ]
1957年北海道生まれ。スポーツライター。明治大学卒業後、出版社勤務を経て、87年からフリー。「Number」「VS.」「優駿」などの雑誌を中心に執筆
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
にゃん吉
2
野球、相撲、武道の計五つのスタジアム(後楽園球場、両国国技館、川崎球場、日本武道館、東京スタジアム)にまつわる沿革、歴史が、さっと読める文体で叙述されていて、面白い一冊でした。メディアのコンテンツとして育まれた巨人の「全国区」の人気と表裏にあった、球界の発展と絡めた後楽園球場の話、戦後の高度経済成長、工業都市として発展した川崎市の歴史と重ね合わせた川崎球場の話、親会社大映と名物オーナー永田雅一氏の盛衰とともに、ひとときの夢のように下町に現れて消えた東京スタジアムの話が、特に興味深くありました。 2022/10/30
YOS1968
0
スタジアムには、言葉で表現できないワクワク感がある。苦しい時代を生きていた人の思いを集約する不思議な装置でもあった。後楽園球場の英断、オリンピックと日本武道館、下町の「光のスタジアム」東京スタジアム。ほんの短い期間だけ駒沢の暴れん坊のステージとなった駒沢球場にも光を当てて欲しかった。2011/06/02