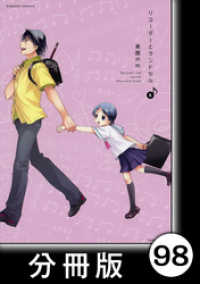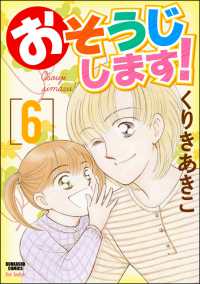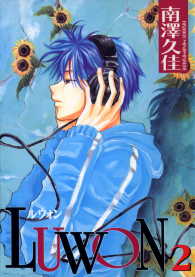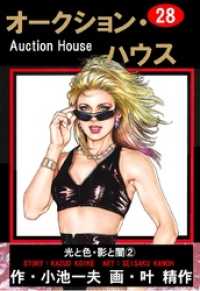内容説明
本書は、新しい構想にもとづく現代的な熱力学のテキスト・参考書である。熱力学をできるかぎり見通しよくかつ論理的に理解することを目指し、伝統的な方法とは異なるアプローチをとる。すなわち、マクロな仕事を主役にする操作的な視点から熱力学全体をとらえ、等温での操作(第二法則)と断熱下での操作(第一法則)をそれぞれ議論したあと、両者を統一する枠組をさがすことで、自然に熱力学の全体像に到達する。理解が困難といわれるエントロピーについても、「エントロピー原理」を中心に明解で生き生きとした位置づけを行なっている。初学者はもとより、すでに熱力学を学んだ読者にも深い理解が得られる最適な書である。
目次
1 熱力学とはなにか
2 平衡状態の記述
3 等温操作とHelmholtzの自由エネルギー
4 断熱操作とエネルギー
5 熱とCarnotの定理
6 エントロピー
7 Helmholtzの自由エネルギーと変分原理
8 Gibbsの自由エネルギー
9 多成分系の熱力学
10 強磁性体の熱力学
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
nbhd
19
人生を踏み誤っている、と思うのだが、40代を手前にした文系あたまの僕はこの本を読んで、物理数学の勉強にマジメに本腰をいれようと考えている。そういう本だ。日本の熱力学史を変えた名著だと言われているけど、僕はその真価をまだ味わえていてない。少なくとも文字は読めるし、理解できる部分もあるけど、まぁわからない。ゆいいつ、感じて、わかっているのは、田崎先生の熱とチャーミングさだ。慣れない理系文体だけど、そこにチャーミー!が宿るとは知らなかった。…まずは、多変量解析。人生を踏み誤っていることは、誤りではないはず。2021/10/20
shin_ash
6
新人が入社してきて統計力学は分かると言うので田崎先生の教科書を紹介してもらった。しかし新人曰くその前に田崎先生の熱力学を読むべしと言う。夜学で熱力学をやった気がするがエンタルピーとエントロピーは関係ないと言われひたすらエンタルピーの話をされた記憶しか無い。一方で情報理論では熱力学からのアナロジーでエントロピーを扱う。そう言う意味では学び直しに丁度よかったと思う。熱力学を操作と仕事で記述説明することに拘った本書は大変わかりやすい。系のマクロな関係の美しさを上手く説明できていると思う。このスタイルのおかげで、2023/07/17
デコボコ
5
円城塔いわく、日本の熱力学理解が飛び抜けているのはこの本のおかげ。 たしかに、たいへん見通しの良い本でした。2014/09/13
kai
3
ミクロな視点をカンニングせずに熱力学を構築している.非常に鮮明な論理で書かれていて,細かいことまでよく注意してくれるので助かる.8章まではちょっと数学書のような雰囲気さえ感じる.9章と10章で応用まできっちり書いてある.2015/01/04
大木貴敬
2
この本では、エントロピーを熱を用いずに定義しているためとてもエントロピーの理解がしやすくなっている。また熱力学をニュートン力学の延長上と捉え、操作的に仕事を主役にして熱力学を構成しています。仕事はニュートン力学で考察できるマクロなエネルギー移動の形態であるため、ミクロなエネルギー移動の形態である熱に比べてわかりやすい。つまり田崎熱力学はわかりやすいということです。熱力学を学ぶ任意の人はこの本を読んで霧が晴れる感覚を味わうべきです。 2024/03/10