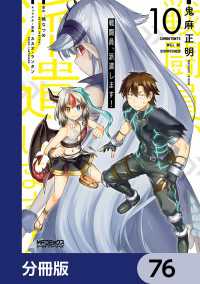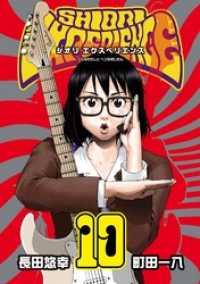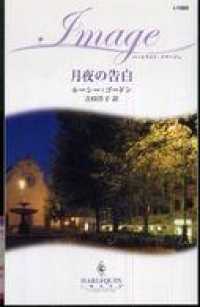出版社内容情報
新井 紀子[アライ ノリコ]
著・文・その他
内容説明
大規模な調査の結果わかった驚愕の実態―日本の中高校生の多くは、中学校の教科書の文章を正確に理解できない。多くの仕事がAIに代替される将来、読解力のない人間は失業するしかない…。気鋭の数学者が導き出した最悪のシナリオと教育への提言。
目次
第1章 MARCHに合格―AIはライバル(AIとシンギュラリティ;偏差値57・1 ほか)
第2章 桜散る―シンギュラリティはSF(読解力と常識の壁―詰め込み教育の失敗;意味を理解しないAI ほか)
第3章 教科書が読めない―全国読解力調査(人間は「AIにできない仕事」ができるか?;数学ができないのか、問題文を理解していないのか?―大学生数学基本調査 ほか)
第4章 最悪のシナリオ(AIに分断されるホワイトカラー;企業が消えていく ほか)
著者等紹介
新井紀子[アライノリコ]
国立情報学研究所教授、同社会共有知研究センター長。一般社団法人「教育のための科学研究所」代表理事・所長。東京都出身。一橋大学法学部およびイリノイ大学数学科卒業、イリノイ大学5年一貫制大学院数学研究科単位取得退学(ABD)。東京工業大学より博士(理学)を取得。専門は数理論理学。2011年より人工知能プロジェクト「ロボットは東大に入れるか」プロジェクトディレクタを務める。2016年より読解力を診断する「リーディングスキルテスト」の研究開発を主導(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ろくせい@やまもとかねよし
きみたけ
もりやまたけよし
rigmarole
sumiyaki