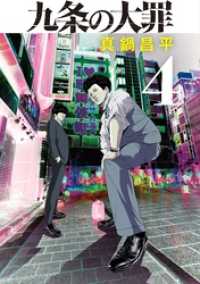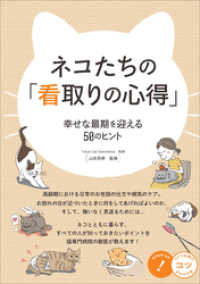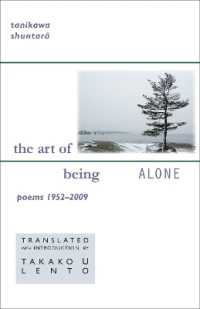内容説明
天皇と将軍が並び立つ日本中世の「王」とは一体何者だったのか?武士=御家人の利益を守るために設立された幕府が、朝廷に学び、みずから統治者たらんとしたとき、武士から王への歩みが始まった。頼朝から戦国大名を経て、徳川幕府が完成するまでのプロセスを、貨幣経済の浸透、海の民の活躍、一神教のインパクトなどさまざまな観点から読み込み、ひとつの骨太な「物語」として提示する全く新しい日本中世史。
目次
第1章 中世の王権
第2章 実情(ザイン)と当為(ゾルレン)
第3章 武門の覇者から為政者へ
第4章 土地と貨幣
第5章 東と西
第6章 顕密仏教と新しい仏教
第7章 一向宗、一神教、あるいは唯一の王
著者等紹介
本郷和人[ホンゴウカズト]
1960年東京生まれ。東京大学・同大学院で石井進氏・五味文彦氏に師事し、日本中世史を学ぶ。専攻は中世政治史、古文書学。東京大学史料編纂所で『大日本史料』第五編の編纂を担当し、現在は、東京大学大学院情報学環准教授。実証的な研究に基づきながら、歴史に「物語」と「人物」を取り戻そうと試みている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
takeapple
8
中世から近世の歴史、平氏政権、鎌倉幕府、法然、一向一揆、島原の乱など。成る程と腑に落ちる。それより何より本郷先生の日本史を取り戻そうという気概が良いではないですか!暗記じゃなくて考えること、歴史に興味を持って好きになるにはどうしたら良いかということ、そのためには物語なのだということ、全くその通りだと思います。2012/12/31
がんぞ
3
葛西三郎清重という源頼朝に仕え後に「奥州惣奉行」に任じられた者がまだ二十歳頃の治承四年、今の東京葛飾区の住居に戦帰りの源頼朝が一宿し、歓待したうちに一人の美女がはべこり「近所に住まうものです、今宵のお相手に‥」と勧めた。吾妻鏡。美女は彼の妻だったが一夜で懐妊した場合、識者は「我が子以上に愛育し男子であれば兄がいても家を継がせただろう」という。「家」は最優先だから/荘園という貴族&宗教権力支配から武士の世への遷移とは「土地を耕すものが自らの所有権を確立する」過程で著者は御成敗式目や評定衆制定を王権確立と見る2024/05/21
mushoku2006
3
本著のメインテーマである、 「2つの王権論」は観念的過ぎてよくわかりませんでした。 それは別として、 本著や、別の概説書で、「悪党」について学習。2014/07/24
おらひらお
3
2007年初版。結構内容が濃い本でした。図書館借用ですが要購入本ですね。やさしい仏教の話が興味深かったですね。取りかかりがやや難解な印象を受けますが、途中からはペースも上がり一気読みの一冊です。学校の先生にもおすすめか。2012/08/08
(ま)
1
当為より実情を 2つの王権論2018/04/08