目次
第1章 音楽とテンポ
第2章 拍子とリズム
第3章 旋律
第4章 音組織と調性
第5章 オーケストラの楽器
終章 総合的分析
著者等紹介
田村和紀夫[タムラワキオ]
1952年、石川県七尾市生まれ。国立音楽大学楽理科を卒業、同大学院修士課程を修了し、音楽学を専攻する。現在、尚美学園大学助教授。芸術情報学部で主に西洋音楽史と音楽美学を担当
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Wataru Hoshii
2
スコアを読むようになってから、クラシック音楽をより深く楽しめるようになった。この本はそのさらに先の扉を開いてくれるもの。スコアに書かれていることをどう読み取ることができるか、という面白さを教えてくれる。例えば、転調する箇所を見ることの重要性。どの調からどの調へ(何度)動くかを見極めること。また、長音階/短音階とは違う旋法(モード)の効果。それを調性のシステムとどう折り合いをつけているかということ(こういう観点からの分析は読んだことがなかったので参考になった)。スコアをさらにじっくりと読み込みたくなる本。2013/05/08
tegege
1
面白い!クラシックを聴きたくなる一冊。2012/11/18
ALBA
1
わたしのような義務教育レベルの音楽知識ではキツいと思いますが、それでも作曲者がどのような意図で音符を組み立てて行ったのか、指揮者・演奏者がそれをどう読み取って演奏しているのかの仕組みの一端に触れる事ができます。特に最終章にあるベートヴェンの「運命」の解説には目から鱗が落ちるようでした。指揮者によってなぜ同一の曲が違って聴こえるかの理由もここにはありますんで、ちょっとのぞいて見るのもありかと。 楽譜がいっぱい載ってますのでそれが読めればどんなに良かったかと思いました(^^;2011/11/14
らら
0
内容がちょっとハードだなと思う部分もあったけれど、クラシック音楽を分析的に聴く入門として、いい本だと思った。作曲家がここまで緻密に計算して曲を生み出していると思うと、1音1音が本当に大切で必要な音だということが強く感じられる。聴衆の立場以外に、指揮者・演奏者の立場で読んでもおもしろい。これをきっかけに、1つの曲をアナリーゼしながらじっくりと聴いてみたい。2016/05/17
O. M.
0
私のような、特別な音楽教育を受けていない一般人にはちょっと難易度が高かったですね。説明のために多数の譜面が引用されていますが、譜面を見慣れていないと直ちにその解説と結び付けて理解するのが難しいのです。音楽のテンポは、部分ではなく一曲全体の中の変化としてみるべき、といった目から鱗の解説もありましたが。。。2015/12/30




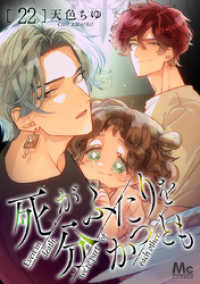
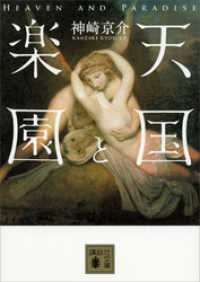
![[新装版]全訳「武経七書」1 孫子 呉子](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0232285.jpg)


