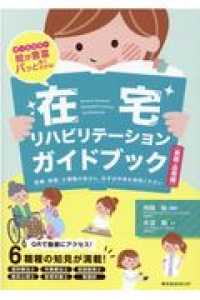内容説明
歴史というものは、手ざわりで感じていかなければいけないところがある―。いまここに息づいているかのような存在感にあふれる司馬文学の登場人物。彼らはどのような思索と経験から生まれたのか。取材手法、史料との向き合い方、自身の精神風土について。創作の裏側を縦横無尽に語る。作家の肉声や書斎の風景が、いきいきと甦るかのような語り下ろしエッセイを、読みやすい大きな字でお届けする。
目次
私の歴史小説(庶民の風土;生活史への興味 ほか)
歴史のなかの日常(トシさんが歩いている;歴史を見る目 ほか)
歴史のなかの人間(見える目と見える場;義経という人気者 ほか)
日本史と日本人(日本的正義感;藩というイメージ ほか)
わが小説のはじまり
著者等紹介
司馬遼太郎[シバリョウタロウ]
1923年大阪市生まれ。大阪外国語学校蒙古語部卒業。60年、「梟の城」により第42回直木賞受賞。76年、日本芸術院恩賜賞受賞。81年、日本芸術院会員。93年、文化勲章受章。著書「国盗り物語」(菊池寛賞)「世に棲む日日」(吉川英治文学賞)「ひとびとの跫音」(読売文学賞)「韃靼疾風録」(大佛次郎賞)ほか多数。96年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
まふ
110
成蹊大学教授江藤文夫氏の質問に対する回答の形で司馬氏の歴史小説の基盤、土壌などについて掘り下げた対談集。氏の小説の発想とその背景、育った環境、歴史を見る目、などについて説得力ある発言がなされる。とりわけ興味深かったのは「古来、日本人の基本は『無思想という思想』であり、時代ごとに渡来した思想、宗教を玩味するものの、新しいものが来れば直ちに乗り換える、それはあたかもフライパンのようなもの」という説であった。その他玩味すべき貴重な見解が展開された。今後も何度か読み直すべき書であると思う。2024/10/22
Shoji
32
司馬史観という言葉があります。司馬遼太郎さん独自の歴史観を指し示す言葉です。何かの書評に、この本が司馬史観を理解する一助になるとの評が掲載されていました。読んではみたものの、司馬史観が分かったような、分らないような、私には結論の出ない一冊でした。ただ、明確に分ったことは、司馬遼太郎さんはとてつもない教養人だということだ。おそらく、歴史上の人物でも、民俗でも、戦場でも城でも、何らかテーマを与えれば、いくらでも話題を広げ、際限なく解説できる教養を持つ人だろうと思う。不世出の作家ではないだろうか。2025/01/20
時代
11
司馬遼太郎の歴史を見る視線を江藤文夫との聞き書きから掘り下げていく。司馬さんの生の感覚が伝わってきて非常に興味深い◯2016/07/19
いちろ(1969aMAN改め)
11
司馬先生と評論家である江藤文夫氏の対談。対談といっても導入部に江藤氏の振りがあり、以降司馬先生が語る、という形式の為、入り込みやすく、読みやすい。講座を聞いているようです。司馬先生が如何に日本、日本人、歴史を見ながら物語を書いてきたのか。とても分かりやすく、意見を逐一丸呑み、モロに影響を受けます。そもそも私などは全肯定で読んでしまう。外国人に日本を説明する為の一つの指南書になるような気がする。戦国、維新、明治広く視点をとりながら読むために良いかもしれません。ていうか、やばい司馬モノ読みたくなる。2014/02/20
塩屋貴之
4
司馬さんは日本や歴史をどう考えてるのか知りたくて読む。一番引っかかったのは、歴史の中の人間、「無思想という思想」(って他の人も言ってた気がするけど)、フライパン的態度と、天皇・世俗権力の二重性への言及。特に歴史の中の人間、ということは、やっぱりそこには人間がいるのだな、と目からうろこだったなあ。2010/04/03
-

- 和書
- インパクトマシニング