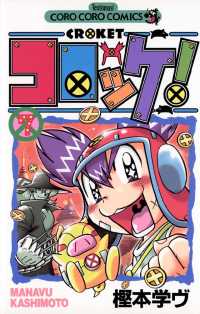目次
第1部 プログラミングがすべてをつくった(インターネットはソフトウェアでできている;インターネットを支えるソフトウェアを知る;プログラミングとは何か;プログラミングと教育;ハッカー精神とは何か―プログラマーに求められる素養と思考方法)
第2部 オープンソースが高めたネットの価値(ライセンスというプロトコル―OSSエコシステムを繋ぐ仕組み;オープンソース化が生んだ変化;企業とオープンソース)
著者等紹介
まつもとゆきひろ[マツモトユキヒロ]
プログラマー、Ruby設計者、角川アスキー総合研究所主席研究員。ネットワーク応用通信研究所、楽天技術研究所のフェローなどを務める。一般財団法人Rubyアソシエーション理事長。愛称「Matz」(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
えちぜんや よーた
68
自分は2015年と2016年にWordCampというイベントの裏方をやった。WordPressというOSS(オープンソースソフトウェアの一種)に対して「貢献」をするためだ。日本語で「貢献」といってしまうと、ちょっと大層な単語に聞こえるかもしれない。ただ自分も経験を踏むうちに、わざわざ「貢献」という言葉を使うのか、肌感覚で分かってきた。本書はその肌感覚を論理的かつ体系的にまとめた本だと思う。(特に第5,6,7章)。「Linux(CentosやUbuntu)なんかタダで使えて当たり前」と 思う方にオススメ。2017/01/13
baboocon
14
超速読で読了。Ruby作者のまつもとゆきひろ氏をはじめとして、インターネットを支えるプログラミング言語をはじめとしたソフトウェアやオープンソースというソフトウェアのあり方の成り立ち、ライセンスをめぐる現状について語る。2016/12/08
俊
9
オープンソース化の成功例は集合知の理想的な利用だと思う。2015/09/12
はるびー
7
オープンソースは、企業にとって秘匿性と独占可能性を犠牲にする代わりに、圧倒的に時間とコストを削減した状態で発想の外から機能が実装されるメリットをもたらす。オープンイノベーションのエッセンスはここにありそう。2017/08/08
hippos
5
「プログラミングと教育」が読みたかったので購入。この章はなかなか良かった。プログラマの僕にとって、「プログラムを書く楽しさ」はぜひ子供に教えてあげたいと思っているので参考になった。その他の章もこれからIT業界を目指そうと思っている若い人には基礎知識として有益だと思う。 表紙に「まつもとゆきひろ」ってでっかく書いてあったので全編まつもとさんが書いているのかと勘違いしてたのはご愛敬です。2015/02/21