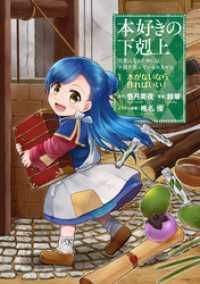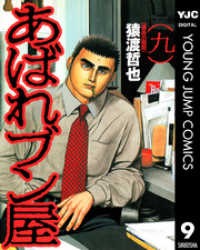- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
近世後期以降、石高制の矛盾と農民の努力から生まれた余剰の穀物を主原料とする醸造業が全国各地で満面開花し、日本の食文化の多様性をもたらしたとともに、地方からの工業化を支える厚い層を形成してきた。本書は、これまでの研究蓄積の少ない地域やテーマもカバーし、醸造業が日本独自の産業化・工業化に果たした役割を明らかにする。
目次
序章 問題の所在(井奥成彦)
第Ⅰ部 醸造業に関わる技術・教育・税制
第1章 明治前中期の酒造技術(青木隆浩)
第2章 戦前期日本酒造業にみる醸造教育とその意義(大島朋剛)
第Ⅰ部補論 明治初期における醤油税制の制定と廃止(石崎亜美)
第Ⅱ部 関東地域の醸造業の展開
第3章 江戸・東京における味噌生産と流通(岩淵令治)
第4章 近世における非農業雇用労働をめぐる一考察
──醤油醸造経営の事例から(谷本雅之)
第5章 近世前期、東京近郊の醤油醸造業と醤油業界(落合功)
第6章 在来産業の製品ポートフォリオ拡張と低級品市場
──1890─1910年代ⅸ油醸造家・髙梨家の地方売りと手印類似品(前田廉孝)
第7章 戦時期ヤマサ醤油における労働環境
──人事課・庶務課の活動を中心に(三科仁伸)
第Ⅲ部 地方における醸造業の展開
第8章 青森県三戸郡・矢幅三次郎家の醤油醸造経営(小杉亮介・花井俊介)
第9章 青森県野辺地の酒造・味噌醤油醸造
──野坂勘左衛門・常吉家を事例として(中西聡)
第10章 近代北陸の醤油醸造業と片口屋(井奥成彦)
第11章 近代における愛知県半田小栗三郎家の経営理念
──人格向上を中心に(伊藤敏雄)
第12章 近代における愛知県知多地方のビール醸造業
──丸三麦酒株式会社の経営活動(橋口勝利)
終章 総括と展望(中西聡)
あとがきにかえて