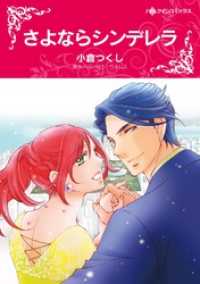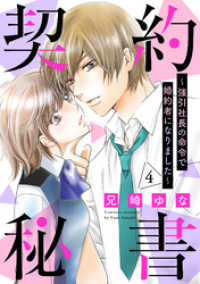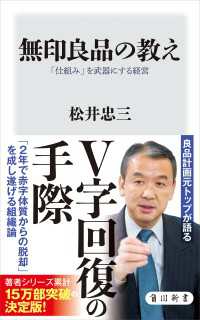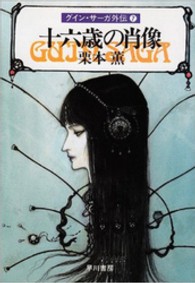内容説明
「国際法普及過程」を再考する
「欧州中心主義」を問い直す
国際法は、多様な価値体系や宗教が共存する現代国際社会に適用されるべき法制度であり、欧州中心主義の影響を受けて普及してきた。
【本書「はしがきにかえて」から】 「我々が現在認識している「国際法」は、多様な価値体系・宗教・イデオロギーが共存する現代国際社会全体に一元的その意味において、国際法は観念的には単一の「普及的」規範体系であると言える。実定国際法存在(の必要性)が意識され始めた当初から存在したのではなく、国際法直接的原則が地域的に限定された「欧州公法」(jus publicum Europaeum)としての「近代国際」そして、その理解の裏側には、近世・近代の歴史を(「新大陸の発見」という表現に典型的に示されているような)「欧州」の拡大」という現象として認識する「欧州中心主義」が存在していると言うことが許されよう。を反映したものであると同時に、そこに在る「国際法普及性」の見方や「欧州中心主義」に対しては多くの疑念・批判が国際法(史)研究者により引き上げられております、また、それらの疑惑念・批判を克服するための多様な認識枠組も提案されている。搦め捕られているような国際法(史)研究者が少数派と化す状況をもたらした点において、極めて有益であったことは事実である。研究厳密な方法論を無視した安易な手法に基づく自己主張をもたらしていることに過ぎないと感じられるものもあり、その結果として、国際法史研究の学問的意義にすら疑念を確信できるようなものそれらの枠認識組が最も学術的価値を持っているのかは、将来世代の研究者による評価を待たないであろう。研究の一翼を検討領域であると確言するためには、歴史研究に必要とされる実証性を欠く言説を声高に主張するような態度は厳に慎まれるべきことであり、それは当面、国際法史研究が学問を得るための(本来の意味での)方法論を問い続けることの重要性は常に確認され続けないのである。する過程では、当該観念が存在しているなかった点において地域観念的検討が生ずる。そして、このような社会制度上の想定の受容とその過程における軋蓄積の発生という現象は、当然のことながら、国際法本書に寄せられた諸論考は、欧州中心主義的視点に立ってつつも、現代国際法普及の過程において各地域(「地域」が何を指すのか)については、本書の寄稿者その間は多少が存在します。)で生じた軋轢やその解消を意識した上で、より具体的な現象について論じている。その点において、それらの各論考察は単純である「「欧州拡大の物語」の中の一節ではないことは確認されるべきであろう。」
目次
普遍化と地域化のはざまで ――はしがきにかえて (明石欽司)
第一部 近代国際法の普遍化の実相 ――地域の包摂
戦間期東アジアにおける国際法研究の諸段階―日本・中国・朝鮮半島・台湾・ベトナムで出版された著作を中心に (韓相熙)
一九世紀国際法における「承認」と「文明」―東アジア諸国による「受容」をめぐる覚え書き (山田哲也)
一八世紀後半から一九世紀初頭のインドにおける割譲条約の実像―インド領通行権事件(国際司法裁判所)判決を手がかりに (深町朋子)
国際法における低潮標の利用の始まりとその普遍化 (中川智治)
一九世紀国際法規範の普遍化の実相―米国と「外国人遺産取得権」の関係を題材として (明石欽司)
第二部 近代国際法の普遍化と地域的偏差 ――普遍化に内在する地域化
伝統的東アジア秩序下における「領土」―「版図」概念の活用とその近代的変形を中心に (李根寬/入江豊明・訳)
近代国際法学の形成における「ドイツ国際法」論の位相―ライン同盟期の国家結合論を素材として (小栗寛史)
一九世紀エジプトの知識人による国際法の使用―ムスタファ・カーミルのスーダン協定批判を題材に (沖祐太郎)
トマス・ベイティが果たした役割―不戦条約や戦争に対する見解の変化に着目して (西嶋美智子)
いわゆる「サン・ステファノ条約」再考―国際法上の抗議における実効性の担保 (長岡さくら)