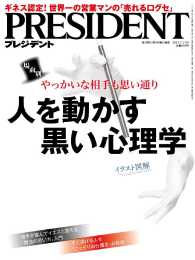内容説明
私たちは互いに無数の差異を抱えている。けれどマジョリティが自分の考えを絶対視したり、その特権性を自覚しないとき、マイノリティは声を奪われがちだ。
でも本当は誰もが、自分はここにいる、と言い始めることができるはず。みな本来、対等な存在なのだから。私たちが声をもつとき、歴史のなにかが変わるだろう。私も、あなたも、誰もがその主役なのだから。
私たちがイキモノとして、のびやかに生きるための羅針盤。二人の芥川賞候補作家が交わす、圧巻の往復書簡。
自分に宛てられた木村さんの手紙を読み、また、木村さんに宛てて自分が書くときもつねに私は願っていた。この書簡に興味を持ち、目を通す人たちもまた、どこのだれかが勝手にこうと決めた「標準」や「規範」の呪縛から解き放たれ、自分が自分であることの信頼を取り戻せるように、と。そうしてはじめて私やあなたは、この世界にとって、よりよい選択をするために手をとりあえる。ーー温又柔「あとがき」より
目次
まえがき
第一章 声と言葉のあいだ
文字から滲む声――第一便 温又柔より
価値の序列――第二便 木村友祐より
自分の居場所――第三便 温又柔より
転換のとき――第四便 木村友祐より
第二章 動物とヒトのあいだ
存在の頼りなさ――第五便 木村友祐より
イキモノたちの時間――第六便 温又柔より
動物たちの側から――第七便 木村友祐より
不均衡への気づき――第八便 温又柔より
第三章 持てる者と持たざる者のあいだ
価値観の根拠――第九便 木村友祐より
だれのための国――第一〇便 温又柔より
固定化する階層――第一一便 木村友祐より
声ある少数派――第一二便 温又柔より
第四章 文学と社会のあいだ
外部に出ること――第一三便 木村友祐より
重要な他者性――第一四便 温又柔より
文学的正しさ?――第一五便 木村友祐より
私(たち)のモラル――第一六便 温又柔より
第五章 性と性のあいだ
線を引くとき――第一七便 温又柔より
無意識の加担――第一八便 木村友祐より
死守したい一線――第一九便 温又柔より
公認された欲情――第二〇便 木村友祐より
第六章 国家と家族のあいだ
国家からの関与――第二一便 木村友祐より
この国の複数性――第二二便 温又柔より
国家へのかかわり――第二三便 木村友祐より
来歴として迫る国々――第二四便 温又柔より
第七章 リアルとバーチャルのあいだ
幸福なネット時代――第二五便 温又柔より
一変した風景――第二六便 木村友祐より
Twitterの可能性?――第二七便 温又柔より
冷笑の対極――第二八便 木村友祐より
第八章 いま、この国で生きるということ
パニックの陰で――第二九便 木村友祐より
この国の当事者――第三〇便 温又柔より
人という起点――第三一便 木村友祐より
かれらの居場所――最終便 温又柔より
あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アキ
踊る猫
千穂
踊る猫
pirokichi



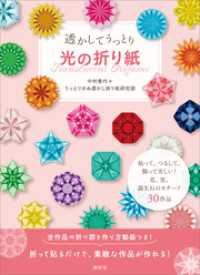
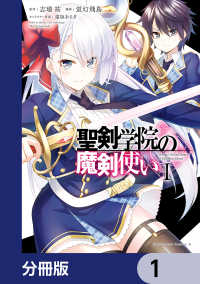
![グローバル経済の歴史[固定版面] 有斐閣アルマ](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0956569.jpg)