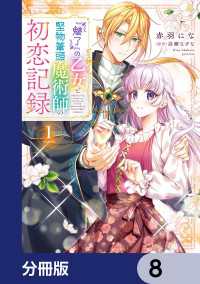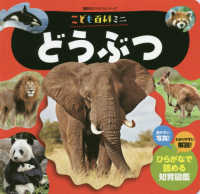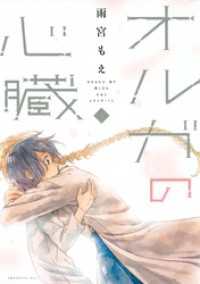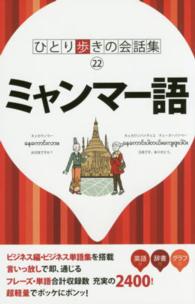内容説明
列強の外圧や植民地支配を通じて「国民」意識を高め、「国民国家」を形成してきた近代のアジア諸国だが、めざましい経済成長や政治変動も相まって各国の国民意識は変容している――。
動画、ポップ音楽など若者文化を手がかりに「一つではない」アジアのアイデンティティを探るユニークな論考。
目次
序章 アジア理解の難しさ
日本社会のアジア理解の課題
一国のなかの多様性
アジアの劇的な変化
若者文化に焦点をあてて
アジアを定義することの難しさ
共有されていないアジア研究の成果
1章 インドネシア――デジタル化とイスラーム化が進行する「想像の共同体」の現在
インドネシア研究から生まれた「想像の共同体」論
ICTによって「上書き」されるナショナリズム
イスラーム・アイデンティティーの活性化
華人系青年たちのアイデンティティー変容
ポスト・スハルト時代の中華文化復権
禁圧政策によってもたらされた華人アイデンティティー変容
2章 シンガポール――エリート主導の無臭アイデンティティー創出と若者の自己探求
「シンガポール人」とは誰か
苦渋の独立
リー・クアンユーの戦略的な国造り
開発を支えるエリート教育
アイデンティティーをテーマにするポップス
3章 マレーシア――国民的漫画が描いたマレー人優先政策下の社会変容
観光キャンペーン映像から考えるマレーシアの過去と現在
漫画『カンポン・ボーイ』『タウン・ボーイ』
ブミプトラ政策の始まり
マハティールのブミプトラ政策認識
マレー人のイスラーム意識の変化
イスラームと近代の折り合い:ポップ・ナシッド
4章 フィリピン――ミュージカルで再解釈された「フィリピン独立の父」
フィリピン国民意識の形成をめぐって
「フィリピン」という国家を「想像」した独立の英雄
国民意識の欠如を嘆くリサール
「フィリピン人とは誰か」を問うミュージカル
映画を通したフィリピン自画像の再構築
5章 タイ――国民意識の根底にある仏教の寛容と非寛容
タイ国民意識の礎となる仏教
現代タイ人の心の奥底にある仏教
タイ仏教についての基礎知識
仏教タブーを描き始めたタイ映画
タイ社会の分断と仏教
6章 インド――「悠久のインド」を語ることの意味
インドの巨大さと多様性
インドの宗教をめぐって
19世紀に形成されたヒンドゥー・アイデンティティー
ヒンドゥー・ナショナリズムとは何か
ヒンドゥー・ナショナリズムと「ボリウッド」映画
近代的な視点から再編集される「伝統」
7章 バングラデシュ――「ベンガル」と「イスラーム」のあいだで揺れる国民意識
変化する「国民意識」の源
ベンガルのイスラーム化
英国植民地政策とイスラーム・アイデンティティー
「東パキスタン」から「バングラデシュ」へ
バングラデシュ独立と再びのイスラーム意識の活性化
グローバリゼーションとイスラーム意識
8章 中国――中国は「一つの中国」なのか
かつて存在した東アジア独特の国際秩序
多民族国家の国民としての「中国人」
「漢人」とは誰か
漢語の多様性
「中華」の世界観
「中国人」意識、「中国ナショナリズム」の形成
対外発信される中国の国民意識
9章 韓国――グローバル化と多民族化がもたらした儒教社会の変容
アジアでまれにみる均質性
近世における国民意識の萌芽
朱子学がもたらした血縁ネットワーク社会
民族史観の台頭
ドラマに見る歴史の語られ方の変化
文化産業振興戦略と広報文化外交
多民族国家としての可能性
10章 モンゴル――騎馬民族ヒップホップが刻む体制転換のトラウマ
類のない社会変容
遊牧騎馬民族の土地感覚
民主化・市場経済化の衝撃
ヒップホップの登場
体制転換を生きる若者の心情
ヒップホップが孕むナショナリズム、排外感情
11章 ベトナム――「南の中華帝国」からグローバル移民ネットワーク国家へ
「ベトナム」という国の形成
中国王朝とベトナムの複雑な関係
近代以前の社会帰属意識
近代ベトナムの国民意識の形成
多民族国家としてのベトナム
越僑:新たなる国民意識形成の源
終章 グローバリゼーション時代のアジアの「自分探し」
「一つ」でないアジア
一国のなかの多様性
グローバリゼーションがもたらした社会変容、個人の意識変化
国民の自己認識の揺らぎ
終わりに:ウイルス危機のアジア
あとがき
索引