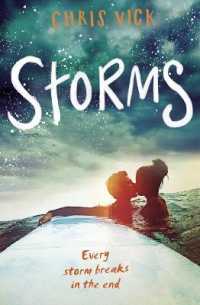内容説明
西洋哲学の概念や思考法のみが純粋なものであるという特権的な意識は、いまや世界的に大きな批判に晒されている。西洋独占主義的な哲学観を輸入した日本が、「日本哲学」を再び検討すべき時期がやってきた。アメリカ、日本、ドイツでハイデガーの哲学、現象学・解釈学から仏教思想・京都学派までを幅広く研究し、日本の哲学史を専攻の一つとしてきた著者が、日本哲学とは何かを、定義・内容から深く問い直し、世界規模の対話に開かれた日本哲学がもつ可能性を総合的に考察する。 【目次】まえがき/序 章 日本哲学の定義と範囲を再考する/第一章 日本・哲学・とは何か/第二章 西洋独占主義的な哲学観を問い直す/第三章 日本哲学の定義を問い直す/第四章 日本哲学の内容を問い直す/終章 世界における日本哲学、日本における世界哲学/参考文献/解説 世界の思考資源としての日本哲学 中島隆博
目次
まえがき/序章 日本哲学の定義と範囲を再考する/西洋独占主義的な哲学概念を輸入した日本/「日本哲学」と「日本思想」の区別の問題/「己事究明」の課題と「二階建て」の問題/十八世紀末における西洋独占主義的な哲学理解の誕生/現在における西洋独占主義的な哲学理解を脱する要求/「日本哲学」は「民族哲学」あるいは「日本人論」ではない/「日本哲学」は主に「日本における哲学」の部分集合である/「世界哲学」という対話の場所における日本哲学/第一章 日本・哲学・とは何か/1 「日本哲学とは何か」と問うことは何を意味しているか/「日本哲学とは何か」に含まれる三つの問い/“philosophy”と「哲学」との類似と相違/「我日本、古より今に至る迄哲学無し」宣言の背景/文化的諸層の同時代的共存と相互変容/哲学的営みは特殊と普遍の間で生じる/2 近代以前の日本に哲学はあったのか? /日本の精神史を振り返って/西洋哲学の輸入に伴う東洋哲学の「思想」化/「思想」は「哲学」に劣るのか/日本における「哲学」概念の特異性/「中国には哲学はない、あるのは思想だけだ」/明治以前に哲学的な論争・議論はあったのか/哲学の仕方はひとつではない/西洋的な傲慢さと日本的な従順さ/第二章 西洋独占主義的な哲学観を問い直す/1 哲学の西洋中心主義と西洋独占主義の問題/擁護しがたい哲学の西洋独占主義/「西洋」と「普遍」の無批判な混同/哲学の普遍性をめぐるジレンマ/このジレンマをいかに克服するか/同化から多様化へ/2 西洋における絶えざるメタ哲学の議論/「哲学」についての共通理解の不在/分析哲学と大陸哲学の多様性/3 西洋独占主義的な哲学観の生成と終焉/「哲学」からの非西洋的な要素の排除/西洋独占主義的な哲学観の系譜/対抗するパラダイムの系譜/西洋中心主義から西洋独占主義へ/ヘーゲルによる西洋独占主義の再主張/パラダイム・シフトの萌芽/4 迫りくる多元的哲学観へのパラダイム・シフト/他性との出会い、そして対話/多元主義者たちによるパイオニア的な仕事/「哲学」の多義性を取り戻す/5 開放に導く生き方としての哲学/古代ギリシア・ローマ人の哲学観/哲学と宗教の二分法/日本における関与的な知のモデル/全心身的な実践、宗教的な動機/6 非西洋の宗教、芸術、哲学──包摂する暴力と排除する暴力のジレンマを乗り越える/非西洋的伝統が直面するダブル・バインド/日本における「宗教」概念の再定式化/「芸術」「美学」概念の再定式化/他者の声を受け入れ、常に解釈しなおすこと/第三章 日本哲学の定義を問い直す/1 日本哲学の競合する諸定義/「日本哲学」をいかに定義するか/マラルドによる「日本哲学」の四つの定義/2 日本哲学についてのいくつかの一般化/「無常」と「主客合一」/抽象的な「理」よりも具体的な「事・物」を重視/一般化は普遍的定義ではない/3 普遍性への特殊な諸アプローチの集合としての日本哲学/「日本」哲学について語るとは何を意味するのか/対話の異種的な空間としての「世界の哲学」/特定の伝統から自由な哲学という神話/「どこからでもない眺め」は不可能である/特殊と普遍のあいだで/多様性と統一性/4 世界哲学の対話への貢献としての日本哲学/特殊を通じて普遍を探究する/自他の特殊性への理解と普遍に向かう「対話」/5 日本における哲学の(主に)部分集合としての日本哲学/「日本哲学」と「日本における哲学」の区別/世界規模の対話に開かれた「日本哲学」/新たな思想潮流の源泉としての辺境/常に再定義される「日本哲学」/第四章 日本哲学の内容を問い直す/1 『オックスフォード・日本哲学への手引き』のトピック選定について/『手引き』の選定原則および神道、仏教、儒教の扱い/明治以降の「西洋哲学」受容と京都学派/日本哲学の未来を見据えたプラットフォームとして/2 『オックスフォード・日本哲学への手引き』概要/論考の成り立ち/第一部 神道と日本の哲学的思考の総合的性質/第二部 日本仏教の哲学/第三部 日本儒教と武士道の哲学/第四部前半 近代日本哲学──京都学派/第四部後半──京都学派以外の近代日本哲学者/第五部 日本の哲学的思考における広範なトピック/終章 世界における日本哲学、日本における世界哲学/欧米言語における近年の日本哲学研究/世界哲学の文脈/日本における世界哲学論史/近代日本哲学についての近年の研究/東アジアにおける日本哲学の研究/日本哲学は西洋哲学導入から始まったのか/世界哲学における日本哲学/「無条件に問う」ことを問う/普遍の両義性/人権と仁義の相補性/欠かせない言語、文化、哲学的伝統の多様性/英語および分析哲学の覇権か?/ドイツ哲学はドイツから引っ越したのか/日本の概念の普遍化/思想を含む哲学、哲学を含む思想/定まっていない思想と哲学の意味と関係/二階建ての脱構築/排除と包摂の狭間で──禅は哲学ではないが、禅の哲学はある/日本哲学は何になるべきか/参考文献/解説 世界の思考資源としての日本哲学 中島隆博/日本すること、哲学すること/「西洋独占主義」という呪縛/無条件に問い、「普遍」を志向する/ハイデガー、京都学派、禅仏教への深い関心/「世界哲学」としての「日本哲学」/哲学し続けることを諦めない/人名索引
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
buuupuuu
horada