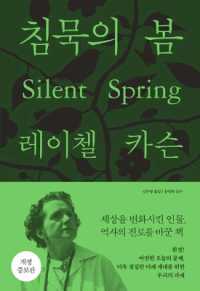- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
客が消えた下呂温泉はなぜ再生できたのか
地域全体で取り組んだ再生戦略から、温泉地復活のヒントを探る
日本の温泉地は長い期間、低迷の時期が続いてきました。
バブル崩壊後、旅行スタイルは団体から個人・少人数へと移行し、その変化に対応できなかった旅館やホテルは次々と廃業に追い込まれました。さらに追い打ちをかけるように新型コロナウイルスの影響が観光業を直撃し、多くの温泉地が深刻な打撃を受けました。
ようやく回復の兆しが訪れ、コロナ禍明けの2024年には、多くの観光客が温泉地に戻り、かつてないほどのにぎわいを見せる地域も現れました。その一方で、観光需要の波に乗り切れず、依然として厳しい状況に置かれている温泉地も少なくありません。
著者は岐阜県・下呂温泉で旅館を営みながら、観光協会の会長として地域再生に尽力してきました。他温泉地と同様に、観光客の減少に苦しんでいた下呂温泉を、“選ばれる温泉地”へと再生させた立役者です。著者は、温泉地を活性化させるには旅館単体の努力だけではなく、飲食店や商店街、行政、観光協会といった温泉地全体が一体となって取り組むことが不可欠だと説きます。
本書では、地域全体の連携を基盤に「顧客マーケティング」「官民連携」「経営改善」という3つの観点から、観光客が何度も足を運びたくなるような温泉地をどのように生み出すか、その具体的な秘訣を明かします。
観光業に携わるすべての人にとって、現状打破のヒントが詰まった一冊です。
目次
はじめに
[第1章]
地方の温泉地・旅館が衰退の一途をたどるなか
地に足の着いた施策を繰り返しⅤ字回復を果たした下呂温泉
「勝ち組」と「負け組」の二極化をたどる温泉地
変化に対応できない温泉地はジリ貧に
解消できない「温泉地格差」
かつてのにぎわいから一転、下呂温泉が陥った窮地
ネームバリューの裏に隠れた地道な努力
[第2章]
似たり寄ったりなイメージの「温泉地」から一歩抜きんでる
マーケティングに基づいて地域の「強み」を発掘
地域マーケティングによって2カ月で宿泊客数が前年同時期を上回る
50年前から蓄積してきた宿泊者データを活用するDMO
データ活用による新たな取り組み
データに基づいた宿泊プランの開発
月に1度の「誘致宣伝委員会」
食べ歩き・街歩きが楽しめる温泉街への変貌とスイーツ事業の展開
データに基づかない施策は自滅の道をたどるだけ
必要なのは地域活性化のためのマーケティング
[第3章]
エコツーリズムとDMOの融合が地域の魅力を最大限に引き出す
地域全体を巻き込んだ「官民連携」の取り組み
観光ブランディングは地域全体で取り組むべき課題
全国初! エコツーリズムとDMOを融合させた「E-DMO」
行政とうまく連携するためのコツ
「データは誰でも見られる」が大前提
宝探し事業――――地域の「宝物」はあなたの街にも埋まっている!
市全体で魅力を再発掘! エコツーリズムの取り組み
各エリアの「色」を活かした観光振興
市民向けの「ワンコイントリップ」の開催
市民の交流から地元への誇りが生まれる
エコツーリズムの新たな試み
[第4章]
従業員のモチベーションやサービスの質を上げる
旅行客が泊まりたくなる旅館・ホテルになるための「経営改善」
旅館やホテルは生産性が低い業界の代表
大型旅館でも客室を絞らないで個人客90%以上を達成した秘訣
個人客のマーケティングによって多様なニーズに応える
部屋食から和洋中3つのレストランまでニーズに対応
コロナ禍でも従業員の採用を強化した理由
トヨタ生産方式「カイゼン」の導入
「1歩1秒1円」でコストを換算
ハウスキーピングのカイゼンで年550万円のコストを削減
予約システム入力作業の標準化で年710万円の削減
目指すべきは「サービスの質を落とさずに経費削減」
カイゼンへの取り組みが従業員の意識を変えた
「人の手をかける部分」と「DXで効率化する部分」を分ける
DXによる改善効果は年2786万円
顧客情報をデジタルでつなぎ、顧客ニーズにスピード対応
人材教育は「マルチタスク」ではなく「スペシャリスト」
スタッフに「ここで働きたい!」と思わせる経営改革
[第5章]
「熱」のあるところに人は集まる
下呂に旅行客を引き寄せたのは温泉と、働く人の「熱い想い」
源泉集中管理方式の下呂温泉はSDGsの最先端
ポストコロナのここ数年が勝負
日本人も外国人も過ごしやすい温泉地を目指して
ワーケーションの場としての温泉地
「定着しない」から「働きやすい」職場へ
業界の「人手不足」を解消する秘訣
温泉旅館でも高賃金は実現できる
「観光地で働く人」はどうあるべきか
これからの観光地に必要な「攻め」の姿勢
おわりに