内容説明
教員の質量低下が深刻化し、教員志望の学生のレベルダウンも著しい。その根底には、教員・生徒・保護者の、学校という場への意識の変容――「逃走」がある。気鋭のジャーナリストが丹念な現場取材をおこない、教育改革に必要な策を提示する。
-

- 電子書籍
- 悪役に正体がバレてしまった【タテヨミ】…
-
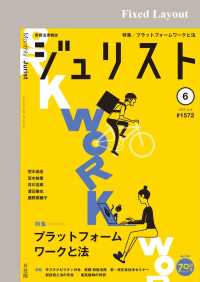
- 電子書籍
- ジュリスト2022年6月号 ジュリスト
-
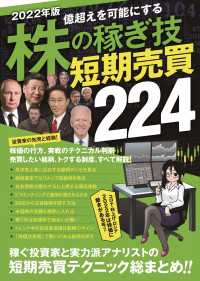
- 電子書籍
- 2022年版 株の稼ぎ技 短期売買 2…
-

- 電子書籍
- ドッペルさん(3)
-
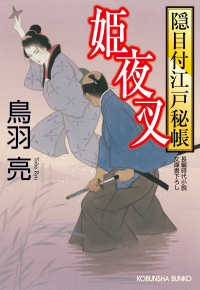
- 電子書籍
- 姫夜叉 隠目付江戸秘帳 光文社文庫



