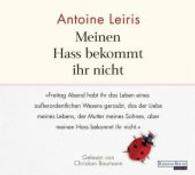内容説明
近年,電力システムにおいてデジタル化が進む中で,IEC 61850が注目を浴びている。本書では,IEC 61850のシステム構成記述言語であるSCLに特化した解説と規格動向を踏まえ,豊富な記述例をまとめた。
目次
1. 序章
1.1 本書のメインテーマ
1.2 SCLの役割と特徴
1.2.1 SCLの役割
1.2.2 SCLの特徴
1.3 SCLの将来性とSCLを活用したエンジニアリング業務の可能性
1.3.1 SCLの将来性
1.3.2 SCLを活用したエンジニアリング業務の可能性
1.4 変電所保護監視制御システム
1.4.1 保護リレー装置
1.4.2 監視制御装置
1.4.3 遠隔監視制御装置
1.5 IEC61850を適用したシステムの構成
1.6 変電所保護監視制御システム構成の変化
1.6.1 これまでの変電所保護監視制御システム構成
1.6.2 IEC61850を適用した変電所保護監視制御システム構成(ステーションバス)
1.6.3 IEC61850を適用した変電所保護監視制御システム構成(フルデジタル)
引用・参考文献
2. 変電所保護監視制御システムのエンジニアリング
2.1 IEC61850のエンジニアリング
2.1.1 SCLにて記述される各種設定ファイル
2.1.2 SCLに基づく設定ファイルエンジニアリングツール
2.2 工事エンジニアリング
2.3 開発エンジニアリング
2.4 エンジニアリングツールと各種設定ファイルの生成手順
2.4.1 トップダウン方式
2.4.2 ボトムアップ方式
2.5 BAPによる機能仕様の定義
引用・参考文献
3. SCLの利活用
3.1 BAP整備の重要性
3.1.1 BAPの粒度
3.1.2 BAPの作成イメージ
3.1.3 BAP整備によるエンジニアリング業務への貢献
3.2 SCLを介した国内のエンジニアリング業務の変化(トップダウン方式)
3.2.1 工事エンジニアリング(IEC61850適用)
3.2.2 開発エンジニアリング(IEC61850適用)
3.3 BAPのSCL化
3.4 監視制御卓画面の自動生成
3.5 ポジション情報としてのSCL活用
3.6 単線結線図作成によるトップダウンエンジニアリングの可能性
3.7 制御ケーブル布設図相当としてのSCL活用
3.8 通信ネットワーク構成図としてのSCL活用
引用・参考文献
4. SCLファイルの構造
4.1 SCLとSCLスキーマの概要
4.1.1 SCLとSCLスキーマの関係性
4.1.2 SCLおよびSCLスキーマ内で利用される命名規則
4.1.3 SCLの全体構造
4.1.4 XSDファイル
4.2 Header要素
4.2.1 Text要素
4.2.2 History要素
4.3 Substation要素
4.3.1 VoltageLevel要素
4.3.2 Voltage要素
4.3.3 Bay要素
4.3.4 ConductingEquipment要素
4.3.5 PowerTransformer要素
4.3.6 TransformerWinding要素
4.3.7 Tapchanger要素
4.3.8 GeneralEquipment要素
4.3.9 ConnectivityNode要素
4.3.10 Terminal要素およびNeutralPoint要素
4.3.11 SubEquipment要素
4.3.12 Function要素
4.3.13 SubFunction要素
4.3.14 EqFunction要素
4.3.15 EqSubFunction要素
4.3.16 LNode要素
4.4 IED要素
4.4.1 Services要素
4.4.2 AccessPoint要素
4.4.3 Server要素
4.4.4 LDevice要素
4.4.5 LN0要素
4.4.6 GSEControl要素
4.4.7 IEDName要素
4.4.8 Protocol要素
4.4.9 SampledValueControl要素
4.4.10 SmvOpts要素
4.4.11 ReportControl要素
4.4.12 TrgOps要素
4.4.13 OptFields要素
4.4.14 RptEnabled要素
4.4.15 DOI要素
4.4.16 SDI要素
4.4.17 DAI要素
4.4.18 Val要素
4.4.19 Inputs要素
4.4.20 ExtRef要素
4.4.21 DataSet要素
4.4.22 FCDA要素
4.4.23 LN要素
4.4.24 AccessControl要素
4.4.25 Association要素
4.4.26 ServerAt要素
4.4.27 KDC要素
4.4.28 Authentication要素
4.4.29 SettingControl要素
4.4.30 LogControl要素
4.4.31 Log要素
4.4.32 GOOSESecurity要素
4.4.33 SMVSecurity要素
4.4.34 Subject要素
4.4.35 IssuerName要素
4.5 Communication要素
4.5.1 SubNetwork要素
4.5.2 ConnectedAP要素
4.5.3 Address要素
4.5.4 GSE要素
4.5.5 SMV要素
4.5.6 PhysConn要素
4.5.7 P要素(Address要素の子要素として使用する場合)
4.5.8 P要素(PhysConn要素の子要素として使用する場合)
4.6 DataTypeTemplates要素
4.6.1 LNodeType要素
4.6.2 DO要素
4.6.3 DOType要素
4.6.4 SDO要素
4.6.5 DA要素
4.6.6 ProtNs要素
4.6.7 Val要素
4.6.8 DAType要素
4.6.9 BDA要素
4.6.10 EnumType要素
4.6.11 EnumVal要素
引用・参考文献
5. ケーススタディとSCLサンプル
5.1 サンプル変電所における変電所構内通信ネットワーク
5.1.1 構成1:ステーションバスとプロセスバスの分離
5.1.2 構成2:ステーションバスとプロセスバスの分離(Proxy接続)
5.1.3 構成3:ステーションバスとプロセスバスの統合
5.2 Header要素の記述例
5.3 Substaion要素の記述例
5.3.1 電圧階級(VoltageLevel要素)の記述例
5.3.2 変圧器(PowerTransformer要素)の記述例
5.4 Communication要素の記述例
5.4.1 SubNetwork要素の記述例
5.4.2 ConnectedAP要素の記述例
5.5 IED要素の記述例
5.5.1 Services要素の記述例
5.5.2 AccessPoint要素の記述例
5.5.3 Server要素の記述例
5.5.4 ServerAt要素の記述例
5.6 DataTypeTemplates要素の記述例
5.6.1 LNodeType要素の記述例
5.6.2 DOType要素の記述例
5.6.3 DAType要素の記述例
5.6.4 EnumType要素の記述例
引用・参考文献
付録 AXMLについて
A.1 XMLによる構造表現
A.1.1 XMLの概要
A.1.2 特徴
A.1.3 XMLの構文(記述方法)
A.1.4 XMLインスタンス
A.1.5 タグ
A.1.6 親要素・子要素
A.1.7 ルート要素
A.1.8 空タグ
A.1.9 属性
A.1.10 名前空間
A.1.11 要素の名前空間
A.1.12 属性の名前空間
A.1.13 デフォルトの名前空間
A.2 XMLスキーマ
A.2.1 XMLスキーマとしての名前空間の指定
A.2.2 XMLとXSDの関連付け
引用・参考文献
付録 BUMLについて
B.1 UMLによる構造表現
B.1.1 UMLの概要
B.1.2 UMLクラス図の表現
B.1.3 UMLユースケース図の表現
B.1.4 UMLシーケンス図の表現
引用・参考文献
索引
感想・レビュー
-
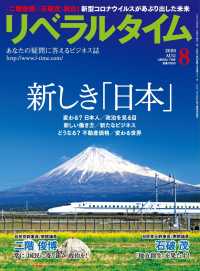
- 電子書籍
- リベラルタイム2020年8月号
-
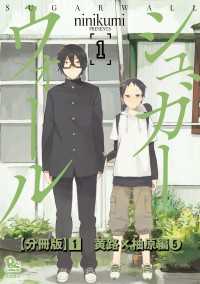
- 電子書籍
- シュガーウォール【分冊版】(1)黄路×…