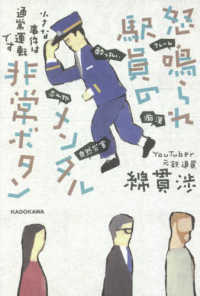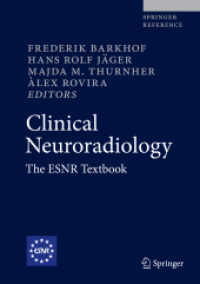内容説明
「機械鍛治の技術を放棄して,文学の道へ志そう.芸術は僕にとっての再生の救いであった」(細井和喜蔵).「女工哀史」といえば「悲惨な労働」のイメージ.でも読めば働く人たちの息遣いが聞こえ,「古典」のイメージが覆る! 当時無名の若者による渾身の内部告発は,現代にこそ有効だ.刊行から100年,作品の魅力を読み解く.
目次
はじめに――無名の若者が残した内部告発の書……………斎藤美奈子
第一章 細井和喜蔵の生涯……………松本 満
第二章 『女工哀史』を読む……………斎藤美奈子
第三章 『女工哀史』の小説版『奴隷』『工場』……………松本 満
第四章 妻としをの「もうひとつの女工哀史」……………斎藤美奈子
あとがき――和喜蔵没後一〇〇年の年に……………松本 満
コラム「女工小唄」――時には叙情詩,時にはプロテストソング……………松本 満
関連年譜
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
相米信者
6
過酷な労働を強いられる女工たちを描いたノンフィクション、細井和喜蔵の『女工哀史』が刊行されて100周年になる。そして、細井和喜蔵が短い生涯を終えて100周年になる。100年経った今、科学技術の発展により日本は豊かにはなったが、ブラック企業・バイト、セクハラ・パワハラの横行、そして格差社会。形は違えど本質的に女工哀史の時代とあまり変わらないのではないか?と感じる。本書は細井和喜蔵の生涯と『女工哀史』の内容、小説版のあらすじ、妻の高井としをの生涯などを分かりやすく説明している。2025/08/05
め
5
「女工哀史」から今年でちょうど100年を記念して岩波から出された解説冊子。細井和喜蔵および内縁の妻としをの生涯もまとめて学べます。 刊行ひと月後に28歳(!)で病没した和喜蔵と、亡くなる3年前に78歳(!)で自伝「わたしの女工哀史」を著したとしを。この歴史すら含めて「女工哀史シリーズ」なんじゃないか、という運命の渦感に圧倒された。 2025/08/26
冬峰
4
いつの時代も資本家ってやつは人件費を削りたがる。たぶん費用面だけでなく、同じ人間に対して理不尽を強いることで優位性を味わいたいのだろうと自分などは思うが、まあそれはこの本には関係ない。女工哀史がモダンガールと同年代であることに、指摘されて初めて気付いた。迂闊。田舎での女工の募集、まんま女衒じゃねえか。最後、著者細井和喜蔵の事実婚の妻に対し、周囲の男たちは和喜蔵を称える一方で冷たい仕打ち。誰も報いない。以前プロレタリアのジェンダーに関する本を読んだが、それと同じく、女の働きはやはり目に入らないようだ。2025/08/14
駒子
3
『女工哀史』気になっていて、ただ、なんとなくハードルが高いので、今年7月に出版されたガイド本を読んでみました。斎藤美奈子さんの指摘はもっともだ、ということばかりでした。女工哀史もそうだけど、妻の高井としをさんの自伝の方が読んでみたくなりました。女を使役する男にも蔑ろにする男にも怒りを覚えます…。2025/09/03
バーチャルヤマバク
1
7月にふらっと読んだもの。えっ!昔も今も労働環境そんなに変わってないんだ!と驚いた。
-

- 和書
- 14歳の恋 〈5〉