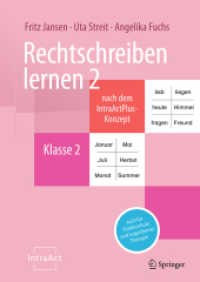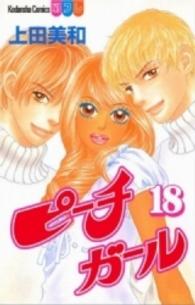内容説明
教師という職業は,なぜこれほどつらい仕事になってしまったのか? 本書は,教師が主体性を奪われ,現在の異常な労働環境へと至った歴史的・法制度的構造を明らかにするとともに,多くの問題が指摘される給特法を徹底的に分析する.教師が子どもと向き合う職業であり続けるために,厳しい現状からの「出口」を示す決定版.
目次
序章 「働き方改革」vs.「教育の充実」の罠──なぜ問題なのか、なにを問題にしなければならないのか?
1 「○○くんだけに付き添っていることはできない」
2 「ささいな日常」の映す本質
3 苦痛にあえぐ教師の声
4 労働者と「聖職者」の分断?
5 本書の構成
第I部 給特法の制定までとその後──なぜ、つらい職業となってしまったのか?
第1章 教員給与の法制史──「あるべき給与体系」をめぐる相克
1 はじめに──なぜ教師の労働条件は重要なのか
2 教師の労働条件の基本原則
3 教員に特殊な手当とルール──給特法と人確法
4 小括──「政治的決着」に委ねられた教員の労働条件
第2章 教員給与の新自由主義改革──二〇〇〇年代以降の制度改変
1 はじめに──教員給与の「屋台骨」の喪失
2 国立学校準拠制の廃止──教員給与法制の屋台骨の喪失
3 揺らぐ労働基本権制約の論理──代償措置の不在状況
4 国立学校準拠制廃止後の教員待遇──東京都における教員給与制度改革
5 小括──「意識」「文化」に還元できない多忙化の要因
第II部 給特法の解剖──本当は何が問題なのか?
第3章 給特法の構造と矛盾──ゆがめられた教職の「特殊性」
1 はじめに──給特法というミステリー
2 労基法上の労働時間規制ルール
3 給特法の構造
4 一九七一年国会審議にみる給特法の立法者意思
5 小括──矛盾だらけの給特法
第4章 二〇一九年改正給特法の問題──迷走する「学校における働き方改革」
1 はじめに──給特法「改正」で働き方改革は進むのか?
2 改正給特法の上限指針
3 捻じ曲げられた一年単位変形制
4 一年単位変形制導入のハードルと決定プロセスの重要性
5 小括──問われる教育の地方自治、学校自治、そして労使自治
第5章 改正給特法における「労働時間」概念の問題──労基法を潜脱する「在校等時間」論批判
1 はじめに──「労基法の労働時間概念」がなぜ重要なのか
2 給特法の特殊ルールをめぐる諸説
3 文科省の示す労働時間概念の問題
4 小括──学校に「労基法上の労働時間」概念のメスを
第III部 給特法問題の出口を求めて──司法による是正と新たな制度モデルへの展望
第6章 司法による教育政策是正の可能性──給特法をめぐる従来型裁判の類型と争点
1 はじめに──「敗訴」の歴史のなかで「新たな訴訟」をさぐる
2 従来の教員超勤訴訟の類型
3 埼玉教員超勤訴訟にみる「労基法上の労働時間」該当性
4 小括──教員の働き方改革における裁判所の役割
第7章 埼玉教員超勤訴訟第一審判決の意義と課題──「画期的」な理由と乗り越えるべき壁
1 はじめに──第一審判決の評価をめぐって
2 第一ステージ──その仕事は「労基法上の労働時間」にあたるか?
3 第二ステージ──賃金請求権(損害賠償請求)は認められるか?
4 教育労働に固有な労働時間をめぐって
5 小括──教員多忙化問題の「出口」を求めて
第8章 学校における働き方改革のオルタナティブ──アメリカにみる教員に固有な勤務時間管理モデルの可能性
1 はじめに──働き方の国際比較からみえてくること
2 アメリカの労働時間法制における学校教員の位置
3 教員の労働基本権と教員組合の地位──ニューヨーク州テイラー法の特徴
4 団体交渉で獲得した「教員に固有の勤務時間管理」──ニューヨーク市学区の団体交渉協約
5 コロナ禍の教員の働き方ルール
6 小括──労働条件決定における労使自治の重要性
終章 教員の働き方改革のあるべき方向
1 給特法のもとでの三六協定締結の可能性
2 不可欠な立法政策
3 教員に固有な労働時間を求めて
4 教師をいじめる教育政策に終止符を
5 「教師が教師でいられない世の中」を変えるために
あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しょこぴ
mokohei
-
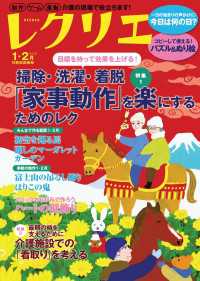
- 電子書籍
- レクリエ 2026年1・2月 レクリエ