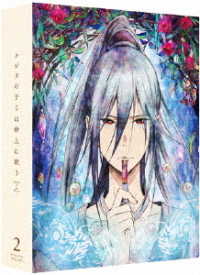内容説明
2050年の図書館はどうなっているのだろうか。現在、大学で図書館情報学の研究と教育に携わっている教員らが今から25年後の2050年の図書館を見据えて、各々の専門の見地から現状と課題、提言等をまとめた一冊。司書だけではなく図書館に関心のある学生・市民にもおすすめ。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
明るい表通りで🎶
28
2050年の図書館は、どんな姿になっているかの論考集。共生社会の図書館の実現に興味がわいた。2025/04/16
まつ
2
図書館機能が自分の仕事に近い概念のため読んだ。現代とAI時代の機能の章を読み、目指すべき姿がイメージできた。 情報提供がメインでなく、利用者が、学び、課題解決、コミュニケーション、創造など活躍することが重要。そのため、利用者ニーズの理解を前提に情報資源を熟知し、AIなどデジタルツールを駆使して利用者を満足させるコーディネーターが不可欠。 ランガナタン『図書館は成長する有機体である』 バーゾール『図書館は、社会的な交流をすすめ、共同社会および文化の質の保持に携わり、そして感性及び知性を刺激する場所』2025/05/04
かおっくす
1
これからの図書館は「総合コーディネート」という役割が期待される。人ひとりに多能化・複脳化を求めていく。機械やAIを導入し、人は人しかできないことのみを行う。2025/11/04
たむ
1
娘の昼寝を見計らって暗い部屋で読んでたので、所々ウトウトしてしまったのが悔しい。これからの司書には「場」としての図書館において、様々な立場の人(高齢者、外国籍の人、認知症の人etc..)をつなぐコーディネート的な役割も担う必要がある。また、カスハラへの対応としてルール自体を緩和してしまってストレスを減らすという方法は意外だった。確かに意外とそれでも問題って出ないものな気もする。電子資料の方が増えるかもしれないこれからの世の中で、それでも紙の書物に私は残ってほしい。それはニーズに合ってないのかな…うーん。2025/10/10
必殺!パート仕事人
0
この本に筑波大の先生が入っていないのが残念。著者のうち2人は筑波大学の院で学んだとはありますけれども。複合型の図書館を作るにも社会教育機関(公民館など)との連携を考えたい方がいいというのにはなるほどです。つくばの研究所との連帯もしたいところ。2025/05/04
-

- 電子書籍
- 最強暗殺者、クラス転移で異世界へ【タテ…
-
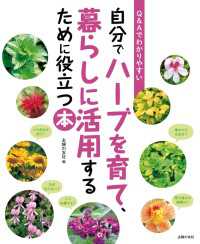
- 電子書籍
- 自分でハーブを育て、暮らしに活用するた…