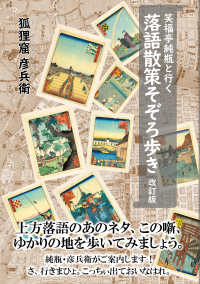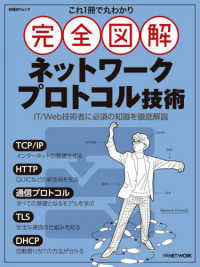- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
日本は群島であり、日本文明は群島文明である。大陸文明的な実体系思考よりも群島文明的な非実体系思考が優勢で、そうした世界観から生命は偶発的なものという感覚や共同主観の構造、革新性をもたらす美意識などが展開され、日本文明が創り出されてきたのだ。そうした日本の歴史的動態を描きつつ、日本の群島文明を形成する東アジアの哲学を「通底哲学」として世界哲学の中に置き直し、より深い文明論として展開する。日本の知の歴史を総合的に理解する、著者独自の日本思想大全。
目次
序章 文明とはなにか/1 道具箱──準備作業のために/本書の叙述の進め方/本書を読み進めるために必要な「概念のあたらしい定義」いくつか/文明は〈2〉の行為である/文明は「利己的な文明子」を使って拡散運動をする/文化は〈2〉から〈1〉に近づくプロセスである/文明と文化の関係/主体は文明子の乗り物にすぎないのか/人間とは多重主体である/アトム的個人と多重主体/2 文明と未開の関係性/なぜ文化ではなく文明なのか/「文明」は悪なのか/ホモ・サピエンスは「文明」を求める/「文明」は客体でもあり、もちろん暴力主体でもある/3 三つの存在様態/生命とは/大陸にも群島にも、三種類の生命がある/〈第一=個別〉〈第二=集まり(集合・全体・普遍)〉〈第三=あいだ〉/「自己」の三様態/「もの」「こころ」「からだ」の三様態/第一章 日本は群島である/1 群島としての日本/群島のつらなりを切り取る/大陸・半島・島/群島は文明論的な概念/2 群島には文明はない/「群島に文明はない」という視座/「礼義」による文明的なふるまい/朝鮮の文明意識の二重性/文明は道徳が中心なのか/大陸文明によって蔑視される群島/《文明》に対する劣等感を持つ群島/日本語とはなにか/3 群島にも文明があるのか/「群島にも文明がある」という視座/関係性のなかの「文明」/梅棹文明論を参照する/4 東西のつながり/「日本」を自律的なものとして語りたい欲望を否定せよ/朝鮮と比較しなければならない/網野善彦による島国批判の問題点/開放系がよかったのか、閉鎖系がよかったのか/5 南北のつながり/南方・北方へのまなざしは弱い/東南アジアと南方へのふるまい/文明は北からやってくるのか/「ヤポネシア」という画期的な概念/「日本ネシア」というあたらしい概念/四本島と「小ネシア」/第二章 日本群島史の時代区分/1 日本群島史の時代区分論/時代区分は可能か、有効か/本書が提起する時代区分/文明論的な日本の時代区分/「大陸開放系文明期」と「土着閉鎖系文明期」/閉鎖系から開放系へ、開放系から閉鎖系へ/日本群島内の要因/2 土着閉鎖系文明I期──縄文時代(紀元前一四〇〇〇年~紀元前八世紀ころ)/縄文のアニマシー(生命感覚)/弓矢の使用/クリやドングリとともに生きる/3 大陸開放系文明I期──弥生時代(紀元前八世紀~三世紀ころ)/大陸文明の急速な流入/環濠と戦争の時代/倭国と邪馬台国/4 土着閉鎖系・大陸開放系文明混合期──ヤマト政権、古墳時代(三~六世紀後半ころ)/土着閉鎖系・大陸開放系、ふたつのベクトルの衝突/なぜ「土着閉鎖系・大陸開放系文明混合期」なのか/「東夷の小帝国」論/騎馬民族征服説と非畜産民論/鉄と出雲/エピデミックと神/5 大陸開放系文明II期──飛鳥、奈良、平安時代初期(六〇〇~九〇〇ころ)/奈良時代の圧倒的な大陸文明化/「東アジア共同体」の三〇〇年/遣隋使・遣唐使・聖徳太子/国家仏教と華厳哲学/律令体制/時代を闘争的にとらえるべきだ/国史の編纂と「見立て」/《文明》に対する劣等感を持つ群島/朝鮮半島との関係/「第一次国風文化化」/桓武天皇とグローバリズム/漢文から怨霊まで/6 土着閉鎖系文明II期──平安、鎌倉時代(九〇〇~一三〇〇ころ)/日本独自の統治文明の誕生/平安時代と鎌倉時代の重要性/思想的なできごと/「国風文化」はあったか/三国世界観と粟散辺土観/三国世界観は朝鮮を排除する/本地垂迹説/武士の生命感覚/元寇の文明論的意味/7 大陸開放系文明III期──室町、安土桃山、江戸時代初期(一三〇〇~一六五〇ころ)/《一》の時代/実体的世界観の主流化/《一》の追求の時代/《一》への志向/「唯一」と「内在」の時代/粟散辺土観と天皇の神国観のハイブリッド/世阿弥の粟散辺土観/秀吉の朝鮮侵略/8 土着閉鎖系文明III期──寛永以降の江戸時代(一六五〇~一八六〇ころ)/分かれる江戸時代評価/「鎖国」と土着閉鎖系文明化/過剰性のアニマシー/儒教の思想統制/9 大陸開放系文明IV期──明治、大正、昭和、平成、令和時代(一八六〇~二〇二〇ころ)/文明開化という激烈な大陸文明化/世界史上もっともラディカルな文明転換/〈第二の生命〉と「全体」/近代における性/戦争と敗戦/日本国憲法の生命感覚/第三章 日本群島と文明のあいだ/1 日本群島には《一》がなかった/日本群島には、統合的で全体的なひとつの理念が欠如していた/日本に《一》がまったくなかったわけではない/統体的理念と「やまとだましひ」/2 日本群島には《人間》がいなかった/日本群島にいたのは「亜人間」である/大文明の《人間》が人間なのか/大文明の《人間》観念に従属する群島/中国には《人間》がいた/群島の《文明》化、《人間》化というプロジェクト/本居宣長の失敗/3 日本群島には要素還元主義がなかった/東アジアの「還元主義的世界観」/日本群島的アニマシズムの反還元主義/4 日本群島には善悪がなかった/日本群島文明はそもそも善悪を考えることができるのか/ヨーロッパとの違い/5 日本群島には歴史がなかった/歴史が破砕されている/実体系の歴史と非実体系の歴史/平安末期から鎌倉時代の時間感覚/不安、アノミーと加速度/道理と加速度──慈円の場合/無常は加速度の概念/静と動/6 日本群島ではなぜ文学が盛んだったのか/加藤周一『日本文学史序説』の重要な指摘/体系的な哲学の不在/日本群島の「哲学的」矜持/「全体」という大文明的イデオロギー/全体的体系から隔てられた日本群島文明/ひとやいのちの多様性を語れるか、語れないか/第四章 日本群島の生命と人間/1 アニマシズムという群島的生命感覚/日本文明の生命感覚はアニミズムなのか/農業という文明の功罪/アニミズムというイデオロギー/アニミズムは全体を想定する概念/天台本覚思想は大陸文明の生命観/「自然との親和」という観念/「万物」はない/アニマシーとは/「群島的アニマシー」の美意識/生命と変革主体/生権力と生命感覚/2 非実体系の存在様態/実体系と非実体系/日本群島の文明は実体的か非実体的か/「ことだま」は実体系、「ことのは」は非実体系/実体系の「たま」/3 非実体系の「かみ」/「かみ」の語源/「たま」は実体系、「かみ」は非実体系/「かみ」のその後/4 「ことだま」と「ことのは」の対立/非実体系の「ことのは」/「仮名序」の「ことのは」/ことばは重要なのか/ことばを大切にしない文明/5 死のアニマシー/日本群島では生命が軽視された/生命の尊重がそのまま人間の尊厳ではない/生への違和感/生はむなしいがゆえに横溢する/夢とうつつ、生と生でないものの区別がつかない/生は悲哀である/死の三様態/臨終のアニマシー/『往生要集』以後/日常臨終の哲学/臨終即平生/「ぼろぼろ」の死/「ぼろぼろ」の美学/第五章 性のアニマシー/1 《文明》と性/性の秩序意識/文明と性の禁忌意識/日本群島文明の性的特質はなんなのか/2 なぜ日本群島では〈女系いのち〉が生き残ったのか/犂と女神/親族制度の問題/3 最初に自我を獲得したのは女性だった/自我は女神のもの/女人先言の国/日本の女神/女性の自我と表現/あたらしいジャンルをつくったのは女/4 〈女系いのち〉の日本群島文明/強靱な〈女系いのち〉とCGP(クロス・ジェンダード・パフォーマンス)/極度に鋭敏な女性たち/5 CGPという文明運動/和歌という究極のCGP的行為/女性と男性の境界があいまい/「男vs女」ではない/CGPは男による女への支配なのか?/多重主体的な「女性性」/6 女の衰退、〈女系いのち〉の生存戦略/鎌倉時代以後の変化──女性が退潮していく/仏教の女性観/第六章 美のアニマシー/1 反逆は美的生命から/保守的な共同主観に対抗する/美意識という〈いのち〉による抵抗/生活のなかの美的フレーミング/審美的な生のフレーミング/民衆もまた美に生きる/美の反逆性に気づくか/日本群島の反逆的個性に気づくか/2 「あはれ」「をかし」「あっぱれ」/実体系の美意識/「あはれ」は〈いのち〉の立ち現われ/本居宣長の「物のあはれを知る」/あはれは当為なのか/本居宣長は大陸文明の哲学者か/『源氏物語』の「あはれ」/負の主体性の束になるということ/「われかのけしき」とはなにか/「あはれ」は分節化の生命感覚/「をかし」は一般化の生命感覚/紫式部と清少納言の違い/紫式部による清少納言批判/悲哀としての「あはれ」/『平家物語』の「あはれ」/「あっぱれ」の〈いのち〉/女性から武士へ引き継がれる/たたかいと美/終章 トランス東アジア哲学のなかの日本群島/1 日本群島には哲学がなかった/世界哲学は大文明の哲学の専横を糾弾する/大陸文明、男性中心主義、人間/西洋vs東洋ではない/性や親族の規範が人間や哲学をつくった/2 通底哲学・非通底哲学とはなにか/transversal=通底/通底哲学=transversal philosophyとはなにを意味するのか/普遍哲学・通底哲学・非通底哲学/東アジアの通底哲学と非通底哲学/日本群島の非通底哲学/より「低い」哲学へ/なぜ李退渓と元暁が通底哲学なのか/3 トランス東アジアの儒学史/通底哲学としての儒学の発展史/朱子学導入のしかたの違い/朝鮮と日本の違い/4 日本儒学の非通底性と東アジア/通底哲学者としての李退渓の重要性/通底哲学概念としての敬と理/日本の非通底性と李退渓/哲学史のアイロニー/5 トランス東アジアのなかの日本仏教/日本群島文明の哲学における天台の重要性/〈華厳・禅・儒ハイブリッド・パラダイム〉/〈天台・浄土・神道・国学ハイブリッド・パラダイム〉/日本群島哲学の文明的特徴/日本群島文明史を思索するための入門的ブックガイド/あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
よっち
terupoterupo
-

- 和書
- どうぶつふうせん