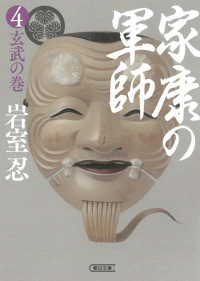内容説明
人類と自然界の「過剰さ」への傾向に関する考察
世界33か国で刊行、オランダ生まれのチリの新鋭による、科学史に着想を得た斬新なフィクション。
「プルシアン・ブルー」 第二次世界大戦末期、ナチの高官らが所持した青酸カリと、西欧近代における青色顔料をめぐる歴史、第一次世界大戦の塹壕戦で用いられた毒ガス兵器の開発者フリッツ・ハーバーの物語。
「シュヴァルツシルトの特異点」 科学史上初めてブラックホールの存在を示唆した天文学者シュヴァルツシルトの知られざる人生。
「核心中の核心」 不世出の数学者グロタンディークの数奇な生涯と、日本人数学者、望月新一の人生の交錯を空想する。
「私たちが世界を理解しなくなったとき」 黎明期の量子力学の発展に寄与した三人の理論物理学者、ハイゼンベルク、ド・ブロイ、シュレーディンガーと、それぞれに訪れた発見/啓示の瞬間。
「エピローグ 夜の庭師」 作者と思しきチリ人の語り手が、散歩の途中に出会った元数学者の庭師との会話や思索を綴る。
科学のなかに詩を見出し、宇宙の背後にある論理や数式が、天才たちの前におのずと姿を現わすかのような比喩が随所に光る。既存のジャンルを軽々と飛び越える国際的な話題作。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
buchipanda3
108
量子力学、天体物理学、数論幾何学、合成化学、20世紀の科学の進展に寄与した学者達の数奇な人生を描いた小説。実名で功績も史実通りだがその人間性を露わにする挿話は主に創作語り。でもそれは実際にそうだったのではと思わせるほど緻密で、人の認識を超越した世界を見出した者の異色な価値観と奇矯な人物像が刺激的だった。波動関数、不確定性原理、既存の概念を解体し、違和感を乗り越える時の人間は不安と狂気に包まれる。女神カーリーの夢の解釈が印象的だ。超越に伴う破壊性、精神の特異点の不可知性への警鐘。ただ、探求は人の業でもある。2024/04/01
ヘラジカ
77
凄い。こんな小説読んだことがない。正確に言うならば似たような小説には数多く出会ってきたが、どれもここまで畏怖させられる作品ではなかった。人類を拡張させ発展させる科学、その一卵性双生児のような大量殺戮の歴史。圧倒的な知性によって遥か遠くへと向かったはずの探求心が、気が付けば人間の深奥へと近づいていたときの根源的な恐怖。この感覚を言葉で説明するのは難しい。少ない文字数で表現するのは尚更困難だ。一つ言えるのは、科学と文学がここまでの強度でもって結びつけられた小説には滅多にお目にかかれないということ。驚異の傑作。2024/02/09
たま
69
【とても辛口御免】途中でやめようかと思ったが薄い本で読んでしまった。エピローグを読むと著者の出発点がわかるし(現代の科学が普通の人間の理解を超えていること)、元数学者の庭師のエピソードは魅力的でこれを膨らませればよかったのにと思う。実際には著者は実在の科学者の言動を極端に奇矯なものとして描き幻覚を見させそれを科学的直観と関係づける。奇矯な言動や幻覚の羅列は退屈で直観は科学の文脈で全然説得力がない。天才ゆえに不適応に悩んだであろう科学者たちの苦悩を思うと著者の誇張は悪趣味に思えた。→2024/06/26
藤月はな(灯れ松明の火)
69
科学がその飛躍と威力を発揮するのは(皮肉にも)戦争だ。戦争での攻撃を生者にも被害を及ぼす大量虐殺への転換となった塩素ガスの開発者、フリッツ・ハーパーを描いた「プルシアン・ブルー」はそれを象徴していると言えよう。残念ながら科学史に明るくないので、どこからが史実で、どこからがフィクションなのかが判別できない。しかし、登場する科学者たちは犬儒哲人、クラーテスのように科学への信仰の余り、人間の枠を超越している。一つ一つの短編がそれぞれ、鮮烈だった為に全ての要素を纏めようとしたかのようなエピローグだけは残念。2024/05/03
美紀ちゃん
68
話題になっていたので読んでみた。科学者、数学者などノーベル賞を受賞した実在の人達の話。短編集。所々に出てくるアインシュタインがやっぱりすごいのだと思った。表紙のこの雲は毒ガス。巨大な緑色の雲が通過したあとは木の葉が枯れ空から死んだ鳥が舞い落ち草は気味の悪い金属のような色に変わったという。開発したフリッツ・ハーバーは戦争犯罪人であるがノーベル化学賞を受賞し肥料を作り農業を豊かにした。空気からパンを取り出した人。すごい本を読んだ。理系の人は興奮するかもしれない。京都大学のすごい日本人が出てきて嬉しかった。2024/03/23
-

- DVD
- 黒い下着の未亡人 通夜の情事
-

- 和書
- 10代 〈上〉