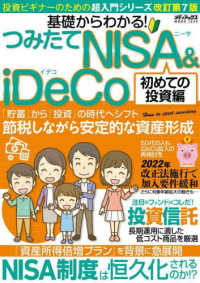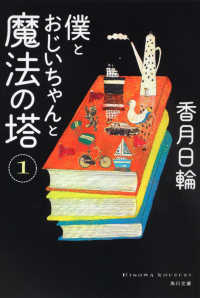内容説明
ダウン症の子どもたちのアトリエ.身体障害者だけの劇団.クラスも試験も宿題もない学校.認知症の老人たちと共に暮らし最後まで看取ろうとする人々.死にゆく子どもたちのためのホスピス…….弱さとは何か.生きるという営みの中には何が起きているのか.著者初のルポルタージュ.文庫版のための長いあとがきを新たに収録.
目次
まえがき
いいんだよ,そのままで――ダウン症の子どもたちのための絵画教室
たいへんなからだ――身体障害者の劇団「態変」
愛のごとく――「人間以上」のものを愛することについて
電気の哲学者――非電化工房代表の藤村靖之博士
山の中に子どもたちのための学校があった――南アルプス子どもの村小学校
尾 道――「東京物語」二〇一三
ベアトリスのこと――子どもホスピス,マーチン・ハウス 前編
ここは悲しみの場所ではない――子どもホスピス,マーチン・ハウス 後編
長いあとがき
岩波現代文庫版のための長いあとがき 「さよなら,ラジオ」のこと
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
メタボン
34
☆☆☆★ ダウン症の子供たちのための絵画教室、身体障碍者の劇団、ラブドールの制作現場、非電化製品を作る人、山の中の自由な学校、子どもホスピス。自分にとっては非日常に映るこれらの場所でも、そこで過ごす人にとってはかけがえのないものだと感じさせる日常が、高橋源一郎の温かな眼差しにより語られている。2023/03/06
naotan
15
最初は世の中で生きていく弱者の取り組みを取材したルポタージュと思って読んでいたはずなのに、気が付くと自分自身の話になっていました。客観から主観への転換が鮮やかです。読んでよかった。2020/10/07
浅香山三郎
11
ダウン症の子ども、子どもの終末期医療のためのホスピス、試験や規則のない学校、障害者による劇団など、社会の大多数からははずれたところで、さまざまな取り組みを進める現場を著者があるく。固定概念や、それらによる意識の支配の外側で、自分の体験を積み、社会について考へることの大事さを全編をつうじて感じさせられる。2024/08/26
原玉幸子
7
子供ホスピス、身体障碍者の劇団、子供主体の自由な学校、ダウン症の子供達の絵画教室、老人の島、非電化発明家等への取材を通じた、「人間が生きるとはどういうことか」の高橋のルポタージュです。勿論取材先へは企画された往訪だったのでしょうが、そもそも「人間が生きる云々」とは高橋も言っていませんし、そこにある何かを(プロの文筆家なのに)上手く表現出来ていません。その意味では、本書は同氏が「図らずも」導かれて出来た本なのかと。(何故『101年目の孤独』との表題にしたのかは、読み落としました。)(◎2020年・冬)2020/12/19
amanon
5
本書のオリジナルが出て十年近くを経た今、本書で取り上げられた取り組みはどうなっているのだろう?自己責任という名目でどんどん弱者と呼ばれる人達(作者はあえて弱者とは言わないけど)が切り捨てられる傾向にある。というか、この時点で既に切り捨てられようとしている現実が垣間見られる。とりわけ形に拘らない南アルプスの小学校の取り組みなど、まさに現代社会に対する真正面からのカウンター的なものだけに、色々と難しくなっていくだろうが、今後も続いていくことを願ってやまない。著者の実家尾道についてのエッセイは身につまされた。2021/09/27