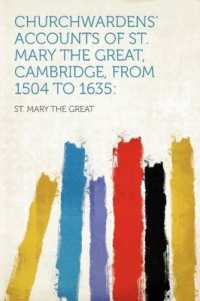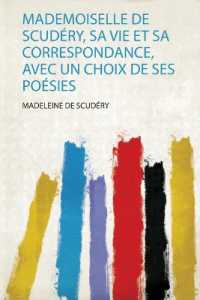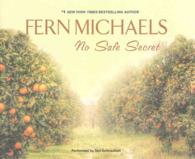- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
生成AIを筆頭に新しい技術の進歩は増すばかりの昨今。SNSや検索エンジンなどの情報は「アルゴリズム」によって選別されている。しかし私たちはそのしくみを知らないままで利用していることも多い。アルゴリズムを紐解くことは、偏った情報摂取に気づき、主体的にメディアを利用する第一歩なのである。本書は、GoogleやAmazon、X、食べログなどを例に、デジタル・メディアやAIのしくみを解説。ブラックボックス化している内部構造への想像力を高めることを通じて、アルゴリズム・AIを疑うための視点をわかりやすく解説、提示する。メディア・リテラシーのアップデートを図る書。
目次
はじめに
第1章 アルゴリズムとは
1 アルゴリズムの日常性
2 アルゴリズムの基本構造
3 アルゴリズムとAIの違い
第2章 アルゴリズムの実際
1 グーグルのランキング・アルゴリズム
2 アマゾンのレコメンド・アルゴリズム
3 食べログのレビュー・スコアリング
4 Xのタイムライン表示アルゴリズム
5 アルゴリズムと「プラットフォーム資本主義」
第3章 アルゴリズムと社会問題
1 認知資源を奪い合うアルゴリズム
2 情報選別の権力となるアルゴリズム
3 マーケティング装置としてのアルゴリズム
4 偽情報・誤情報を拡散するアルゴリズム
5 ユーザーを商品化するアルゴリズム
第4章 アルゴリズムとブラックボックス
1 ブラックボックスとは
2 誰がブラックボックスを作るのか
3 アルゴリズムの公開は可能か
第5章 アルゴリズムのメディア・リテラシー
1 メディア・リテラシーとは
2 メディア・インフラ・リテラシーの可能性
3 アルゴリズムを相対化する視座
おわりに
-
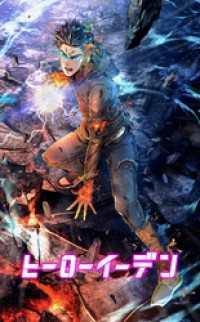
- 電子書籍
- ヒーローイーデン【タテヨミ】15話