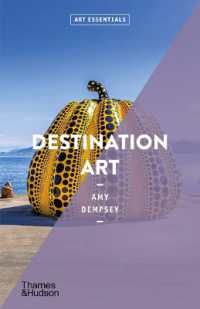内容説明
二人の巨人と辿る戦後80年間の魂の遍歴
戦後80年間の日本人の魂の遍歴を、江藤淳・加藤典洋とともにたどる試み。小林秀雄賞の歴史家が放つ、初めての「文芸批評」。
<上野千鶴子さん推薦
「戦後批評の正嫡を嗣ぐ者が登場した。文藝評論が政治思想になる日本の最良の伝統が引き継がれた思いである。」>
国破れて小説あり
――敗けてから80年、
再生する日本が「青春期」に悶えた記憶を
老いたいま、どう受けとるのか。
文芸評論の巨人ふたりに倣いつつ
太宰治から村上龍、春樹まで、
戦後文学の最も高い尾根から見晴らす
私たちの ”魂” の現代史。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
122
江藤淳も加藤典洋も戦後文学に正面から向き合った評論家だが、やがて文学を生んだ母体である戦後史自体に引き寄せられていった。明治以来の大日本帝国が失敗に終わり、再出発した民主国家日本が無条件に正しいという批評の前提に対する疑問が生じたのか。しかし戦前生まれの江藤はGHQによる日本人洗脳史観に取り憑かれ、戦後生まれの加藤は学生運動の失敗体験から9条擁護固守派の空虚さを糾弾した。文学批評と同じ手法で歴史認識に挑み、その複雑怪奇さに自爆した感が強い。歴史家をやめたと自称する著者は、そこに自分と似たものを見つけたか。2025/06/25
ころこ
43
「歴史の研究者は数多い。しかし、江藤のように歴史を生きる人は少ない。」加藤『アメリカの影』の仮想論的だった江藤に仮託した思いは、著者が歴史の研究者を辞めたと宣言した思いと同一だろう。歴史とは、事実の羅列ではなく物語である。とすれば、文学から戦後を考えることは歴史を生きることになるのではないか。江藤と加藤は文学から暗闇を掘って歴史に、著者は反対に歴史から文学に辿り着いた。前半は柴田翔、庄司薫を論じているところが興味深く読める。学生運動で受容されたこれらの作家は、同世代が実存的に語る対象で、他の世代は置いてけ2026/01/02
hasegawa noboru
26
太宰治と江藤淳<繊細なふたりの文学者は、遠く隔たったまま、ともに自死によってその一生を終えた。このすれ違いが示すように、私たちの国ではある時代の切実な体験が、世代を超えては伝わらない。><かつて母ないし女性に喩えられた、流れた過去をただ忘却し、あるいは祈ることで赦すばかりの「歴史のない」この国の構造は、いよいよ強固になってゆくように見える。>その通り。そんな中、二人の文芸批評家を通して時々の文学作品を取り上げ精緻に分析して改めて日本の戦後史をたどり直す。こんなことがまだ可能だったのかという驚き。2025/06/22
どら猫さとっち
14
戦後史を見直す、または歩き直すために、著者が選んだ人物は江藤淳と加藤典洋。江藤淳はあまり読んでいないし、加藤典洋は読んだことがある。江藤淳が知らない僕でも、わかりやすく解説してある。江藤淳が村上龍を痛烈に批判したのは、わからなくはない。またふたりとも、太宰治から戦後について語っているのが興味深い。江藤は自ら人生の幕を引き、加藤は6年前に世を去った。ふたりの存在は、著者だけでなく、私たちにも必要だっただろう。2025/08/25
tharaud
11
早くも忘れられつつある戦後史を次に繫ぐ試み。江藤淳は、たしかに名前はよく聞くものの実際に読んだことはなかった。書くことへの誠実さや成熟についての本でもある。歴史を知らないことへの開き直りが当然になった時代への鋭い批判だ。2025/11/08