内容説明
近年、中高生の英語力を伸ばしている東京都。その背景には一体何があるのか。
「話すこと」の評価が行われずに来たのは、適切な方法が見つからずそれができなかったからにすぎない。現在は、ICTや既存の蓄積されたノウハウの活用などの工夫により、それが可能となっている。英語は実技の側面が強い。暗記や読解は苦手でも、聞いたり話したりするコミュニケーションは得意な生徒もいる。そのような生徒を適切に評価しないのは不作為による過誤とさえ言えるのではないか。
スピーキング・テスト――いまやらなければ、日本の英語教育はさらに10年遅れてしまう。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Riopapa
4
いろいろと反対意見の多いスピーキングテストだけど、実施している側からの説明。実際にこれで東京都の生徒の英語力が上がっていけば、スピーキングを授業の核にするということに説得力はでてくるだろうと思う。2025/04/29
taverna77
1
英検3級以上の東京都の中学生60.7%/英語話者は世界で15億人/都入試リスニング導入は1997年度~/同スピーキングは2023年度~/ブリカンは2028年度までの契約/ESAT-Jにはいわゆる正解はない/受験者の積極的な発話について、できたことを積み上げて評価/ESAT-Jは目標に準拠した評価を行うテスト/IRTの考え方により採点結果を統計的に処理/合理的配慮を要する生徒に特性に応じた12種類の対応/CEFRのA2に達する受験生の割合25.3%/自分について解答する問題が出題、積極的に解答する生徒が増え2025/05/06
-

- 電子書籍
- デブとラブと過ちと! 53 恋するソワレ
-

- 電子書籍
- この本は僕の経験値を生んだ【タテヨミ】…
-
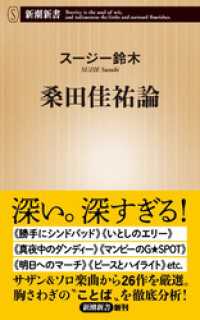
- 電子書籍
- 桑田佳祐論(新潮新書) 新潮新書
-
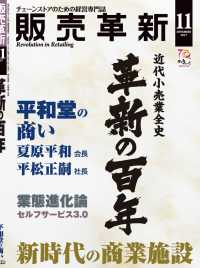
- 電子書籍
- 販売革新2017年11月号 - チェー…
-

- 電子書籍
- 空飛ぶタイヤ(上)




