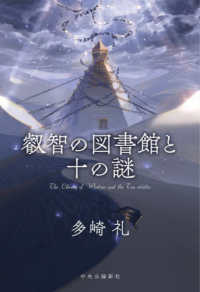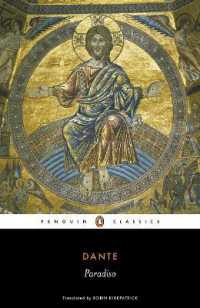内容説明
史記、漢書、三国志、後漢書……元史、明史。中国では、前王朝の歴史を次の王朝が国家をあげて編纂することが多かった。これらは「正史」とされ、統べて二十四史と呼ぶ。中国史の根本史料であり、ここから歴史が記されてきた。
本書は、正史の起源から現代まで、各書の特徴や意義、歴史を追う。さらに、日本の史書との差異や、清史をめぐる中華民国と中華人民共和国の編纂方針の対立など、時の政治の影響を受けた問題を記す。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
130
中国の正史とは革命で滅亡した前王朝の歴史を、次の王朝が自らの正統性を証明するものとして編纂してきた。しかし最初から決められたわけでなく、国が作ったり私撰もあり、長期間かけ編んだものあれば雑なやっつけ仕事も珍しくない。それが2千年も続けられたため権威が生じ、いつの間にか正史になってしまった。逆にいえば過去を否定し現王朝の正統性の宣伝を延々繰り返してきた結果、中国では勝者による歴史の書き換えが当然視されたのだ。万世一系の日本では歴史が武器になる考えそのものがなく、中国との歴史認識論争でやられっ放しのも当然か。2025/06/23
サアベドラ
38
史記から清史稿に至る中国の正史のそれぞれの来歴と特徴を簡潔にまとめた新書。2025年刊。日本では史記と三国志がもっぱら有名だが、いずれも私撰であり彼の国では漢書のほうがよりオフィシャルなものとして重視されたという。日本人にとってこれらの正史はごく当たり前のものとして捉えがちであるが、冷静に考えれば近代歴史学が発達する以前から一つの文明で膨大な量の歴史テキストが生産され、読み継がれていたということはそれ自体が驚異であり、改めて中国という国は文字 (漢字) の国であることが思い知らされる。2025/09/30
まえぞう
36
中国史関係の物語を読んでいるので、書店で見かけた岡本先生の著作を手にしました。史記から始まった中国の正史、三国志までの4作は個人によるものだったのが、南北朝を経るなかで「正当」を意識して官選になり、次第に二十四史にまとめられていく流れが理解できます。2025/08/05
よっち
33
前王朝の歴史を次の王朝が国家をあげて編纂することが多い中国で正史とされる二十四史。その正史の起源から現代まで、各書の特徴や意義、歴史を追う1冊。紀伝体で記された『史記』『漢書』『三国志』から、裴注という転機や戦乱により断絶していた時代があって、唐時代に正史としての意識されるようになったこと、朱子学などの影響や民国期以降の『新元史』や『清史稿』、台湾の『清史』、正史の関連文献として『資治通鑑』なども触れていて、どのように中国の正史が形成されていったのか、全体像を把握するのに分かりやすい1冊になっていました。2025/05/16
Toska
29
自らの歴史を全て文字にして書き残したい、という中国文明の執念には驚くべきものがある。それら数多の史書の中でも背骨の役割を果たす「正史」が本書のテーマ。史書の成り立ちそのものがすでに滋味豊かな歴史なのであり、非常に読み応えがある。司馬遷の個人的な情熱に支えられた『史記』。正史編纂を国家的事業として定着させた唐。活力と実用性にあふれた宋朝の史書。考証学が全盛を極めた清朝。等々、権威主義的でとっつきにくい正史という書物から、それぞれの時代精神が垣間見える。参考文献が充実しているのもありがたい。2025/12/05