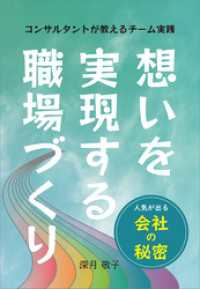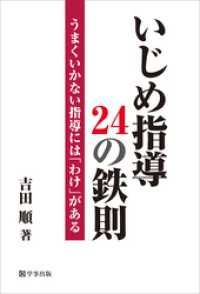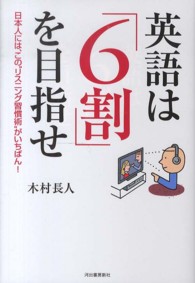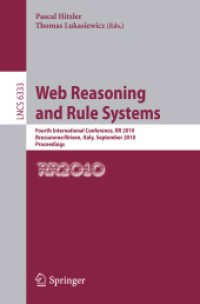内容説明
立ち読みの歴史は読者の歴史。かつてない読書史!
日本特有の習俗である「立ち読み」。一体いつ、どこで始まったのか? その歴史を丹念に辿ると、江戸から明治にかけての「書物の近代化」、そして「読者」の誕生が見えてくる! 国立国会図書館でレファレンス担当を15年務めた著者がその技術を尽くした野心作
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
135
国立国会図書館に奉職され、図書館史や出版史にも詳しい著者が、「立ち読み」という日本独特の習俗を分析する。なぜ欧米には立ち読みがないのか、何時から始まったのかなどの考察を通じて、座売り(閉架式)から陳列販売(開架式)への書店の形態変化や、音読がデフォルトだった江戸時代から、立ち読みによって黙読が習慣化される歴史が見えてくる。私自身は、1996年にジュンク堂難波店が「立ち読み厳禁 座り読み歓迎」の標語の下、店内に多くの椅子を配備した感激が忘れられない。その戦略にまんまとハマり、購入本がどんどん増えたけれど…。2025/06/24
ヒデキ
45
「立ち読み」子ども時代から行ってきた行為をその歴史から語られてこちらが、ワクワクしてしまいました。 「雑誌屋」によって日本に広がった雑誌文化が、雑誌の立ち読み‥本の立ち読みという文化になったのかなとも思いますし、まず日本の識字率の高さが、黙読による立ち読みを可能にしたのかな? 書店員経験のある身としては、今の書店に多い広い通路も意味あるんではないかなと思ってしまいました2025/04/30
よっち
35
日本特有の習俗「立ち読み」はいつどこで生まれ、庶民の読書文化を形作ってきたのか?これまで注目されてこなかった資料を発掘し、その歴史を描き出す1冊。「座売り」(閉架式)だった江戸時代の本屋、日本人の識字率と明治維新による「本の身分制」の解体、ニューメディア「雑誌」の登場、書店の店舗形態の変化、謎多き近代出版史を博捜するなかで浮かび上がってきた読む本を自ら選び享受する「読者」の誕生、そして万引き犯との攻防や立ち読みに対してハタキをする概念など、立ち読みという概念が生まれていった過程がなかなか興味深かったです。2025/05/26
みつ
29
「立ち読み」をキーワードに、江戸時代から今日までの出版形態、書店の業態の変遷を辿る。いくつか抜書きすると⚫︎江戸時代の和綴じ本は平積み。⚫︎明治になっても、座売り(閉架式)で本を販売。⚫︎江戸時代には浮世絵など一枚ものの絵があり、「立ち見」はあっても「立ち読み」はない。⚫︎黙読の習慣が立ち読みが成立する条件。⚫︎立ち読みは個人主義的、主体的で積極的な行為。⚫︎雑誌の興隆が立ち読みを広げる。⚫︎「雑誌の時代」の終わりとともに立ち読み文化も終焉を迎えつつある。等。年表も含め繰り返しが多いが、その分親切な造り。2025/08/06
まさ☆( ^ω^ )♬
22
先日読んだ、三宅香帆「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」もかなり真面目な読書史であったが、本作も「立ち読み」という行為の視点からの読書史という事で非常に楽しめた。たまたまだったが、読書史についての本に続けて出会えたのも何かの縁。読書史は面白い。もっと色々と知りたいと思った。個人的には、鹿島茂「神保町書肆街考」がお勧め。かなりのヴォリュームですが。2025/08/12