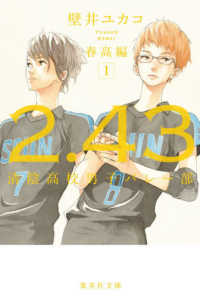内容説明
誰もが抗えないのに、なぜ老いは否定されるのか。ボーヴォワール『老い』を読み、老い衰え自立を失った人が生きる社会を構想する。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ネギっ子gen
67
【人は老いる。老いて衰える。やがて依存的な存在になる。人は人の手を借りて生まれ、人の手を借りて死んでゆく。そういうものだ。そのどこが悪い】ボーヴォワールの「老い」を通して、自己嫌悪させる社会のからくりを暴く書。巻末に、引用・参考文献とボーヴォワール略年譜。「あとがき」で、<1970年に『老い』を刊行したときにはボーヴォワールが知らなかったこと、彼女の想像が及ばなかったことを21世紀に生きる私たちは知っている。それはボーヴォワールに限らずすべての個人が背負う歴史的限界であり、後から来た者の特権である>と。⇒2025/06/20
本詠み人
32
この本はボーヴォワールの『老い』を読み、他人事ではなく自分事として老いを探求する上野先生の最新刊だ。『老い』自体未読な私だが、11章で紹介されているアメリカのベティ・フリーダンの書く『老いの泉』の方が、今の私にとって同調できると思った。社会的役割を果たしながら生涯学習し、自己コントロールを失わないで様々なことに挑戦する。でも弱く出来なくなったらそれを甘受する。女性学から向老学へと進んだ上野先生の、アンチエイジングにアンチを唱える明晰な文章を興味深く読んだ。私も最後まで自分らしく生きそして死にたい。2025/10/06
ケイトKATE
22
2021年7月に『100分de名著』で、上野千鶴子が解説したボーヴォワールの『老い』が放送された。番組を観て、ボーヴォワールが老いを徹底的に分析していることに畏怖を感じた。本書は、番組テキストを元に、上野千鶴子が老いを忌避する現代社会を厳しく批判して、老いても自分らしく人生を全うできる社会を提言している。本来、人間は依存的な存在として生まれ、依存的な存在として死ぬものである。エイジズム(年齢差別)に陥らず人生を全うしたボーヴォワールと、自分の人生を生きている上野千鶴子に勇気をもらった。2025/12/24
hasegawa noboru
22
今、生きている現実として「老い」がある。今日72歳の誕生日を迎えるはずだった妻は2か月前にがんで逝った。これほど身につまされて読んだ同世代上野の本はない。62歳のボーヴォワールが書いた『老い』をコロナ禍中に逢って手にしたという73歳の「わたし」(著者・上野)が解説紹介しながら考察する。<わたしが読みたかったのはこの本だったのだ><老人になるとは情けなくもいとわしい経験であることをボーヴォワールはくりかえし述べてきた>。ボーヴォワールの母の老いと死を巡っての章では、著者自身の父の死の記憶に重ねて考察する。2025/07/14
冬峰
8
全15章、取り上げたテーマはどれもでかい。ボーヴォワールとサルトルの老いや看取りから、日本の介護制度、性別によるケア担当の偏り、安楽死と「自己決定」のあやふやさなど現代の問題を扱う。とにかく若さ至上主義の現代社会は、若者たちには老いへの恐怖を与え、老人たちからは尊厳や生きる意志を奪う。そこにも性別の差は深く影響する。どうあがいても老いは来る。しかも超高齢社会。社会が老人を中心に置くぐらいのことをしないと、構成員の価値観は変わらないだろうな…。2025/08/14