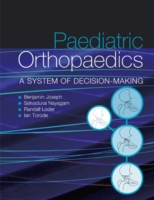内容説明
徳川家康による都市建設の当初から、江戸の水道は高低差を緻密に計算し、複雑な地形を利用する形でつくられてきた。中心部の小石川上水、それを発展させた神田上水、そして玉川上水を基盤とした水道は、明治以降には近代化され引き継がれてきた。急速な工業化や関東大震災からの復興、戦後復興・高度成長を経て水道がいかに拡張され、また経営されてきたか。江戸・東京の経営史を専門とし、東京都水道局に長年勤務してきた著者による、世界屈指の都市の決定版水道史。 【目次】プロローグ/I 江戸時代/第1章 家康と水道/第2章 天下普請の時代/第3章 城下町・江戸と神田上水/第4章 玉川上水の新設/第5章 上水経営の実際/II 明治時代~現代/第7章 近代水道にいたる道のり/第8章 近代水道の成立と関東大震災──拡張の始まり/第9章 大東京と水道/第10章 拡張に次ぐ拡張の時代──戦災復興期から高度経済成長期まで/第11章 量から質へ──低成長時代から現在まで/あとがき/索引
目次
プロローグ/本書の特徴と新たな視点/本書の構成と内容/Ⅰ 江戸時代/第1章 家康と水道/1 家康の江戸入り/江戸の位置/貧弱な江戸城/2 江戸・東京の自然地形/水道と地形/武蔵野台地/東京下町低地/3 江戸城周辺の地形/日比谷入江と江戸前島/江戸前島の現在/4 江戸入り直後の工事──最初から水道を整備/最小限の工事/最初に造られた千鳥ヶ淵と牛ヶ淵──飲料用の貯水池/小石川の利用/日本橋方面と神田一帯の給水需要──商工業の誘致も/平川付替と道三堀の開削──日本橋川のカーブと鎌倉河岸付近の等高線/5 カスガイに付着したカキ殻──埋立予定地にあらかじめ水道を布設/第2章 天下普請の時代/1 江戸の天下普請/天下普請と水道/埋め立てられた日比谷入江──西丸下・大名小路・外濠・溜池/町割の時期/通町筋の確定──不自然な屈曲の理由/2 第二次天下普請/谷筋を掘り広げた桜田濠/江戸舟入堀と八丁堀舟入──江戸前島を活かした港湾施設/本格化する第二次天下普請/3 本郷台の開発と平川放水路/駿河台の宅地造成/平川放水路と堤防の築造/阿倍正之/4 第三次天下普請から神田川整備工事まで──谷筋を利用した外濠/第三次天下普請/第四・五次天下普請と外濠整備/明暦大火と埋立地の開発/神田川が水路に──万治三年の御茶ノ水の開削/第3章 城下町・江戸と神田上水/1 小石川から神田上水へ/神田上水/小石川と神田上水の関係/2 上水の布設ルートの検討/地形図と樋線図からのアプローチ/地形図への樋線の投影/3 小石川上水と神田上水のルート/懸樋の架けられる前と後/本郷台(駿河台)と神田上水──神田上水の幹線ルート/発掘報告と『貞享上水図』/道路が先か、水道が先か?/4 江戸図と神田上水/『武州豊嶋郡江戸庄図』と樋線/5 神田上水の樋線網/神田上水の目的地──神田・日本橋地区への給水/神田上水と地形/江戸舟入堀の船舶給水施設/第4章 玉川上水の新設/1 水道需要の増加と限界に達した神田上水/市街の拡大/経済を刺激した参勤交代/水運網の発達/八丁堀と霊巌島──水道の役割/2 玉川上水の新設/江戸と武蔵野/玉川上水の開削/玉川兄弟は請負業者/新たな水源開発と給水区域/3 玉川上水と地形/尾根と谷、微高地を活かして/江戸市中の玉川上水/4 玉川上水と野火止用水/二度の失敗と野火止へのルート/等高線の分布にみる玉川上水と野火止用水/「失敗」の意味と「史料がない」ことの意味/5 玉川上水の拡張/明暦大火からの復興/四上水の開通/神田上水の助水堀/玉川上水の拡張とその効果──八丁堀と霊巌島は神田上水系から玉川上水系に/少し余力の生まれた神田上水/廃止された四上水/江戸市中における玉川上水の配分/樋・桝・水番人/上水の使われ方/埋立地に上水を送るには/第5章 上水経営の実際/1 江戸上水の経営/江戸上水の経営理念と経営上の価値──永続性の重視/クビになった玉川兄弟/2 上水経営の仕組み/公(おおやけ)による経営──上水を管轄していた幕府の組織/江戸の都市行政と自治のシステム/上水の実務──町人が実施/自治的組織の活用/3 上水経営のための財務システム/現代に通じるシステム/独立採算/受益者負担の原則──石高割と小間割/大規模なメインテナンス──『玉川上水留』にみる虎ノ門外の補修工事/天保四年の玉川上水・赤坂柳堤通りの工事/弘化三年・虎ノ門外の入子型樋桝工事/安政江戸地震の復旧工事/4 『上水記』と石野広通/江戸で発生した「上水毒物混入」の浮説とパニック/田沼意次と松平定信/石野広通と『上水記』/5 現代につながるシステム/第6章 武蔵野台地の井戸と分水/1 武蔵野台地と井戸/降り井の一種が〝まいまいず井戸〟/降り井のメインテナンス──異なる費用負担の方法/熊野井戸普請文書──「五ノ神まいまいず井戸」の修復/「七曲り井」の修復/費用負担の違いの背景/2 新田開発と分水/玉川上水と新田/武蔵野の新田開発と分水/小金井付近の分水(小金井新田分水と梶野新田分水)/分水の建設および維持管理費の負担/公的負担と受益者負担の組み合わせ/新田開発と川崎平右衛門/Ⅱ 明治時代~現代/第7章 近代水道にいたる道のり/1 東京が引き継いだ江戸の水道/水質問題/上水組合の消滅と明治初期の地方制度/2 水道改良に向けて/具体化する水道改良/渋沢栄一と水道改良──東京水道会社/東京水道改良設計書/3 市制町村制と三都の特例/東京府から東京市に移管された水道改良/玉川上水の敷地所有権問題/4 中島鋭治による設計変更/5 鉄管の問題/国産か輸入か──徽章事件というスキャンダル/鉄管不正納入事件/当時の工事従事者/6 三多摩の東京府編入と水道の関係/第8章 近代水道の成立と関東大震災──拡張の始まり/1 近代水道の管路網/2 近代水道の配水系統/高地と低地/自然流下管/ポンプ圧送による高地への配水/3 二重のループ化と隅田川東岸への給水/4 関東大震災と東京水道の復興/大きな被害/管路被害と地形/5 拡張と重なった震災復興/第一水道拡張事業/積極的な管網整備/帝都復興と一体で進んだ水道の拡張/第9章 大東京と水道/1 隣接五郡の人口急増/東京北部から始まった増加/人口増加と水道施設の拡張/放任給水から計量給水へ/2 隣接五郡の水道/東京市を取り囲む町営・民営の水道/我が国初の民間水道会社──玉川水道株式会社/3 買収された玉川水道/玉川水道の株主は実業家や成金/玉川水道の営業成績/大東京の発足と玉川水道の買収──水道に海水が混入/会社・株主の抵抗/4 戦時体制下の拡張事業/第二水道拡張事業/第三水道拡張事業/第10章 拡張に次ぐ拡張の時代──戦災復興期から高度経済成長期まで/1 東京の爆発的な拡大と水道──江戸・東京の水不足体質は四〇〇年も続く/戦後から高度経済成長期の水道──施設整備を中心に/2 戦後復興とインフレ/水道の戦災復旧──水道施設の復旧(応急漏水防止/鉛管叩き潰し)/GHQと東京水道/札幌市の場合/日本国憲法の下での水道事業/3 戦争で中断していた拡張事業の再開/水道応急拡張事業/第二水道拡張事業/淀橋浄水場の移転・廃止と副都心計画/相模川系水道拡張事業/4 新たな拡張の時代へ──利根川水系の開発の本格化/5 水源は多摩川から利根川に/厳しい水源状況は続く──第一次フルプランと第一次利根川系水道拡張事業/第二次利根川系水道拡張事業/最盛期を迎えた水道施設整備と高度成長の終焉/安定してきた水道需要と構造的な渇水/水道事業を支えた料金改定/第11章 量から質へ──低成長時代から現在まで/1 水道サービスの質的な向上/送配水管網の充実・給水所の整備/配水管の強靱化と漏水率の劇的な低下/安全とおいしさの追求──高度浄水処理の普及/2 東京の産業構造の変化と工業用水道の消長/産業構造の転換/東京の工業の発展/東京の工業用水道の展開/3 多摩地域の発展と水道の都営一元化/多摩地域の住宅地化/戦前の隣接五郡と戦後の三多摩/多摩地区の都営水道一元化/4 水道をとりまく環境の変化/臨海副都心開発と八ッ場ダムの完成/5 これからの水道/あとがき索引
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Go Extreme
horada
Teo
-
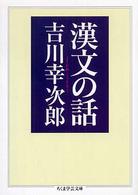
- 和書
- 漢文の話 ちくま学芸文庫