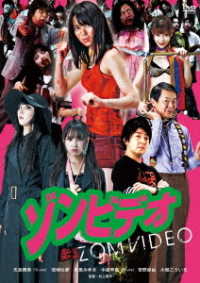内容説明
明治20年代に高輪台の学舎に学んでいた主人公岸本捨吉は、年上の繁子との交際に破れ、新しい生活を求めて実社会へ出て行く。しかし、そこで遭遇した勝子との恋愛にも挫折した捨吉は西京への旅に出る――。作品の行間には少年の日の幸福の象徴である桜の実にも似た甘ずっぱい懐かしさが漂い、同時に恐ろしい程に覚醒した青春の憂鬱が漂う。「春」の序曲をなす、傑れた青春文学である。(解説・三好行雄)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
新地学@児童書病発動中
116
島崎藤村の自伝的な作品。主人公の捨吉が大学を出て、社会に出ていくまでを描く。作者は詩人でもあるので、この小説のあちらこちらに詩的な感性を感じた。特に彼が桜の実を拾う場面はその感性が生かされており、美しく切ない。きめ細かな文章で描かれる明治の日本の姿に限りない郷愁を覚えた。この頃は捨吉と同じように、日本も若かったのだ。北村透谷を初めとして、日本の新しい文学を切り開いていった人たちの姿が活写されているところが興味深かった。捨吉は胸の中に抱える憂鬱を何度も自覚する。この気持が後の作品の伏線のような気がした。2016/10/13
優希
85
自伝的私小説で青春の香りがします。鬱々としながらも成長したいと願う捨吉に共感せずにはいられませんでした。年上の繁子との恋に破れ、新生活を求めて社会に飛び出すことで新たな現実に希望を見たかと思うとそういうわけでもないように見えます。新たな仲間や恋にも挫折したのは苦しい自意識に襲われたからのように感じました。覚醒した青春を送るからこその憂鬱があったのでしょう。丁寧な風景描写の優しさ、心の葛藤が美しかったです。何処かに懐かしい桜の実が感じられる作品でした。2016/03/30
ちぇけら
16
河岸にさいた桜が散り、川のながれにのってたゆたう花びらに似た恋が、小さな蝋燭をかすめる。ぽうっと火がついて、やがて人知れず消えてしまう。春は、そのちっぽけな火を消してしまいたい衝動と、それすら畏れてしまう弱さのいりまじった季節だ。恋心と挫折、逡巡。春のため息は、とても甘くてすこしだけ冷たい。ひとり暗い部屋で名前をよぶことしかできなかったあの人の記憶は、ため息とともにはきだされた蒸気となって空にのぼっていく。2019/04/02
そうたそ
12
★★★☆☆ 著者の自伝的な作品にして「春」の序曲的な位置にあたる作品とのこと。「春」は未読だが、こちらから先に読めて良かったかもしれない。若さ故の苦悩や葛藤もあるが、どちらかというと本書は先への希望を感じさせるような内容で、伸びやかに描かれたことが感じ取れる。圧巻の文章ではあったが、思っていたほど面白くなかったという印象。とりあえず、記憶の薄れないうちに、ここから繋がっていく「春」を読んでいきたい。2023/02/06
sabosashi
11
明治の近代文学の初期においては、大きな可能性が秘められていた。 篠田浩一郎の言を待つまでもなく、「我が輩は猫である」と「破戒」とがもし、その後のニホンの文学史を引っ張っていったなら、より風通しのよいニホン文学が成り立っていたにちがいない。 つまり、反自然主義と純然たる自然主義、という二作品である。 しかし残念ながらニホン文学はそのへんを履き違えてしまったことは、中村光夫とかいろいろなひとが述べている。 そこで藤村である。 2021/08/09