内容説明
「認知行動療法は,雑多具体的な方法の集合体であり,その背景理論仮説も数多く存在し,ひとつの体系立った療法ではない」――だからこそCBTは,理論と技法をフレキシブルに組み合わせ,効果的な方法をクリエイトできる。本書の舞台は子ども×学校。あるときはスクールカウンセラー,またあるときは開業セラピストとして,データ分析を駆使して悩める人たちに知恵と勇気を授けていく。
「特定の話しかしない子」「お腹が痛くて学校を休みがちな子」「動くことがままならない子」,「スピーチ恐怖の女子中学生」など多彩な事例を紹介しながら,データ分析とケース研究の両輪で子ども×学校の悩みをときほぐす。ケースカンファレンスを再現したユニークなCBT事例集。
目次
第1章 認知行動療法の基本的な考え方――その歴史と理念
第2章 データで読み解くスクールカウンセリング――統計分析
第3章 スクールカウンセラーを定義する――学校でのポジショニング・介入のアウトカム
第4章 認知行動療法の事例検討会――5つのケースとディスカッション
事例A-特定の話しかしない子
事例B-お腹が痛くて学校を休みがちな子
事例C-自閉症スペクトラム症(ASD)でパニックを起こす子
事例D(前編)-動くことがままならない子
事例D(後編)-動くことがままならない子
事例E-スピーチ恐怖の女子中学生
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しげ
4
「子ども×学校の困りごと」というサブタイトルから、軽めの事例の紹介が多いのかと思いきや、自死、強迫症状、統合失調症など、重い事例が多く紹介されており、とても興味深く読みました。統合失調症の女の子の事例は、拒食や弄便、自傷他害を含むこだわり行動などがあり、こんなに重い症状のクライアントもカウンセリングで扱うのか、そして改善へ導くことができるのかと驚きました。エッジとユーモアの効いた文体で読みやすかったです。2025/09/30
ちー
2
2010年から不登校率は3倍以上になり、スクールカウンセラーへの相談は4割弱で最も功を奏したとされるのは8.3%教職員からの相談も一般企業と比べ8割低。いかに日本でSCが役に立ってないか述べる。5つの事例ではCBTを用いて学校適応へ導いている。個人セラピーだけでなく、教職員が見逃しているメンタル不調児をスクリーニングしたり、コンサルテーションや子どもに役立つ他システムに繋げるケースワークも担う。 テクニック的には、腹痛予期と実際の的中率を出させたり、本人スマホ使用してビデオフィードバックしたり2025/04/11
まさき
0
家族が明らかに心の病を患っており、薬での対処に限界を感じたので読んでみた。サブタイトルを見落としており、スクールカウンセリングの内容だったので、期待した内容と少し違ったが、実際の症例とその対応の例はとても興味深かった。普段目にすることはほとんどないが、こんな世界もあるのだな、ありふれた病気なのだなと感じさせられた。2025/05/08
-

- 電子書籍
- 新装版 はじめてのGTD ストレスフリ…
-
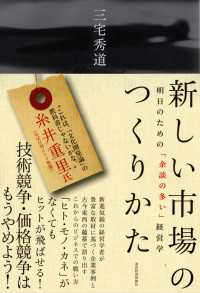
- 電子書籍
- 新しい市場のつくりかた







