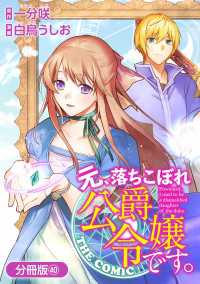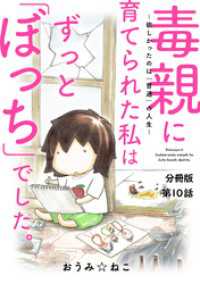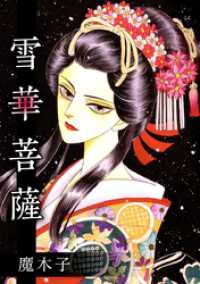内容説明
歴代中国王朝が鋳造した数千億枚に上る銅銭.世界史上極めてユニークなこの小額通貨は,やがて海を越え,日本を含む中世東アジアの政治・経済・社会に大きなインパクトをもたらした.銅銭はなぜ,各国政府の保証なしに商取引の回路を成り立たせてきたのか.貨幣システムの歴史を解明してきた著者が,東アジア貨幣史の謎に迫る.
目次
はじめに──貨幣を選ぶ人々
第一章 渡来銭以前──一二世紀まで
銭の常識
還流しない通貨
原子通貨
溶かされる銅銭
良貨は駆逐されず
一一世紀、硫化銅製錬の革新性
二〇〇〇億枚の古銭
第二章 素材としての銅銭──一二世紀後半以降
布・米遣いの平安日本
過低評価される銅銭
異朝の銭
素材としての中国銭
紙幣に追い出される銅銭
絹の疋から銭の疋へ
元朝の「紙幣本位」制
海を越える銅銭
銅銭を溶かす利益
銭建て取引の普及から定期市へ
素材なのか貨幣なのか
函館志海苔の埋蔵銭
第三章 撰ばれる銅銭──一五世紀以降
公式通貨消滅の一五世紀中国
日本列島での硫化銅鉱開発
東寺の「米価」は何を示すのか
兵士と銅銭需要
日本銅の登場
模造銭ラッシュ
銅銭の色が決め手──古銭と新銭
撰銭という問題
東アジアに広がる撰銭
基準銭と通用銭
日本新鋳の銭
純銅の和製模造中国銭──きわだつ永楽銭の多さ
宋銭で取引される明代
古銭模造と倭寇──結節点としての福建南部
開元銭専用の南京
一六世紀の永楽銭
ベトナムにおける中国銭流通
銅銭流通の重層化
古銭の過高評価
多層化する環シナ海の銭貨
第四章 ビタ銭の時代──一五七〇年代以降の日本列島
倭寇の終焉
撰銭令の変化
米遣いの復活
精銭の空位化
ビタ銭の登場
列島産新銭としてのビタ銭
貫高制から石高制へ
公認されたビタ銭
領国内の公式鋳銭
領国製古銭輸出
第五章 古銭の退場──一七世紀以降の東アジア、自国通貨発行権力の始動
真鍮銭の登場
銀代替のための鋳銭
良貨万暦銭の挑戦
一六一一年、南京銭騒動
北辺防衛のための鋳銭
史上最大の古銭溶解
ベトナムの日本製古銭ブーム
街道整備と寛永通宝鋳造
寛永銭鋳造再開とビタ銭の消滅
最後の宋銭流通
東アジアにおける自由鋳造の終焉
第六章 貨幣システムと渡来銭
英領ベンガルの銅貨
小額通貨の大問題
補助通貨と原子通貨
銅銭の帝国
民の便のための通貨
商品としての銅銭
東アジアの銀貨幣
マリア・テレジア銀貨──もうひとつの渡来古銭
物価と通貨
通貨と市場
あとがき
主要参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
skunk_c
へくとぱすかる
よっち
さとうしん