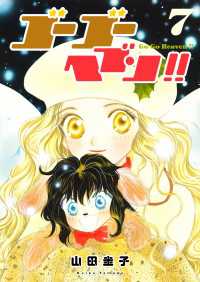内容説明
『日本経済新聞』(朝刊)2025年4月12日、『外交』2025年,vol.91、『公明新聞』2025年7月7日等に書評掲載
米中の覇権争い、あいつぐ戦争。
試練の時代に日本外交はどこへ、どう向かうべきか。
戦後に吉田茂が残した名言がある。
《戦争に負けて、外交で勝った歴史はある》
この言葉は、戦前、戦争に反対し、戦後は外交によって敗戦からの再建と国際社会への復帰に道筋をつけることになる外政家だからこそ口にできた言葉である。
本書が探るのは戦争をせず外交で平和的に問題を解決するための要諦である。
現実主義と理想主義、地政学と戦略論などの理論、E・H・カーやキッシンジャーらの分析に学ぶ。
また陸奥宗光、小村寿太郎、幣原喜重郎、吉田茂、そして安倍晋三らの歩みから教訓を導く。
元外交官の実践的な視点から、外交センスのある国に向けた指針を示す。
序 章 外交とは何か
外務省極秘調書『日本外交の過誤』/外交か軍事か?/外交の定義/外交の起源と外交慣行・外交思想の形成/外交官の使命
第1章 日本外交史の光と影
3つの時代区分
1「調和」の時代(1853~1912年)
開国外交/近代日本外交の始動/「坂の上の雲」をめざした明治日本の外交/四人の外政家/主権線と利益線/日清戦争と陸奥外交/日英同盟論と日露協商論/日露開戦とポーツマス講和会議/韓国保護国化と伊藤の統監就任/明治の戦争が残したもの
2「攻防」の時代(1912~31年)
明治モデルの限界/原敬を失った大正日本/ワシントン体制と軍の反撃/協調外交と強硬外交/統帥権干犯問題
3「崩壊」の時代(1931~45年)
満州事変/「昭和維新」/外務省革新派と三国同盟/日米交渉/振り子原理と幻の日米首脳会談/ジョージ・ケナンの批判
第2章 戦前の教訓と戦後の展開
1「崩壊」の原因
陸軍の独断専行/真のリーダーの不在/外交「崩壊」の原因
2「外交優先」の時代(1945年~)
第3章 法と力
1外交の現場たる国際社会の本質
「法の支配」の脆弱性/自然権と自然法/「力」の視点
2リアリズムとリベラリズム
台頭国家による国際秩序への挑戦/権力と国際秩序/現実主義か理想主義か?/アメリカ外交の理想と現実/理想主義的現実主義
第4章 内政と外交
カギを握る内政/世論と外交/政治体制と外交/外交一元化/錯綜する利益の国内調整/外交の透明性/外交文書の公開
第5章 国益とパワー
国益とパワーの関係
1国益論
死活的国益/力の論理と自由の価値/日本の国益
2外交とパワー
パワーとは何か?/核兵器と「相互確証破壊」/「強制外交」と「力の行使」
3外交実務の要諦
(1)全体性/(2)両立性/(3)持続性/(4)直接性/(5)相互主義/(6)合理性/(7)正当性/(8)戦略性
第6章 戦略と地政学
戦略とパワー/大国関係と戦略/「封じ込め」/「デカップリング(切り離し)」と「デリスキング(リスク低減)」/「戦略的競争」と「競争的共存」/「戦略的安定」と「戦略的パートナーシップ」/戦略の背景にある地政学/米国の海洋覇権に対する中国の挑戦/中国の海洋戦略/自由で開かれたインド太平洋/米国の海洋安全保障戦略
第7章 外交力の要諦
「外交力」とは何か?
1情報力
外交における「情報」とは何か?/情報収集の要諦/機密情報の入手/陸奥宗光の情報分析/情報と政策の関係/偽情報と情報戦
2交渉力
米朝首脳会談の教訓/信頼と譲歩/「同意しないことに同意する」/力を欠いた「悪しき宥和」
3外交感覚
「外交感覚」とは何か?/ナショナリズムとバランス感覚/「空気」に沈黙した外交感覚
4外交官の「個の力」
外交官の職務と役割/外交官に必要な資質/知力/誠実さ/勇気
終 章 試練の日本外交
戦争の教訓からの出発/国際協調による国益確保/「国際協調」への批判/「積極的平和主義」/外交手段としてのODA/東アジア秩序の構想/アメリカ主導秩序の終焉/日中関係のマネージメント/グローバルサウスを味方に/米国の力と意思/国家安全保障戦略の転換/時代の空気感/日本有事と抑止力/「核なき世界」をめざして/外交センスのある国家