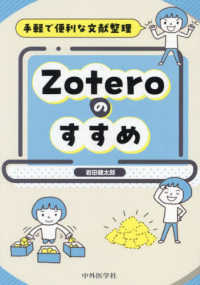- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
「文章を読むのが遅く、内容も頭に入ってこない」
「説明を聞いても、要点がつかめない」
「人も気持ちがわからず、うまくコミュニケーションできない」
と悩む人は多い。
これらの症状の根っこには「読解力の低さ」が隠れています。
読解力とは、文章や発言の意味を正しく理解する能力。
意味だけでなく、その背景にある真意や意図までをも見抜く能力。
この読解力が貧弱だと、「書く」「話す」「判断する」「伝達する」「問題解決する」といった、あらゆるアウトプットで誤作動が生じます。
その結果、仕事や生活、人間関係が思うように運ばず、無駄な労力を要し、ミスやトラブルも頻発します。要するに、人生がうまくいかないのです。
一方、読解力のある人はどうでしょうか?
読解力のある人は、文章や会話から正確に内容を理解したり、物事の本質を瞬時につかむことができます。理解が早いだけでなく、それを伝達する力も高いです。
対人関係では、相手の気持ちや空気を適切に汲み取りながら、気持ちよい建設的なやり取りができます。
会議では複雑な議題をわかりやすくひもといたり、問題の本質をズバリ言い当てたりします。商談やプレゼンでは相手の言葉から素早くニーズをキャッチし、成約に至る確率を高められます。
その結果、「あの人は頭がいい」「理解力が高い」「仕事ができる人だ」という印象や評価を得ることができるのです。
つまり、読解力は、私たちの仕事や生活を含む人生を支えているOS(基盤システム)のようなものなのです。
本書を読み、実践することで、読解力は飛躍的に高まり、驚くほどの能力を発揮できるようになり、人生は劇的に好転することでしょう。
※カバー画像が異なる場合があります。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アキ
livre_film2020
今庄和恵@マチカドホケン室コネクトロン
Nazolove
よっしー
-
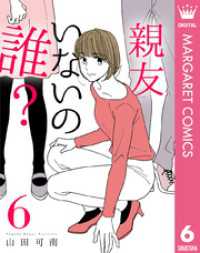
- 電子書籍
- 親友いないの誰? 6 マーガレットコミ…