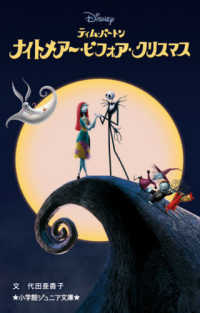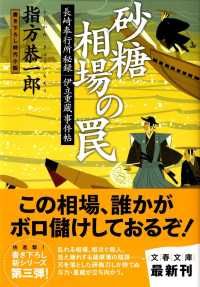内容説明
子どもが学校に通い始める際、保護者と子どもはどのような経験をし、そこにはいかなる問題が生じているのか。幼児教育と就学にかかわる接続の課題が「小一の壁」として注目されるようになった社会的経緯を明らかにしつつ、保護者へ調査により、その実相を描き出す。家庭と学校との接続、社会保障の新たなあり方について提言も行う。
目次
序章 「小一の壁」への関心の高まり
1.一年生になったら――一九六〇年代と今
2.「小一の壁」の打破は「喫緊の課題」
3.就学の社会学
4.通時的視点と多様な家族状況への目配り
一章 就学の二つの意味と日本の就学制度
1.「就学」の二つの意味
2.日本における就学の制度的特徴
3.一九一〇年代までの就学をめぐる国家と保護者の軋轢
4.在学問題としての長期欠席・不登校問題
5.就学問題の再浮上
二章 就学に関する社会学的研究と本書のねらい
1.就学に関する社会学的研究
2.現代日本における就学をめぐる軋轢の発生
3.本書のねらいと四つの問い
4.教育臨床社会学の方法論
三章 就学問題の社会的構築――小一プロブレムと小一の壁
1.「小一プロブレム」の指摘
2.学校不適応問題としての「小一プロブレム」
3.「小一プロブレム」における保護者の位置づけ
4.就労問題としての「小一の壁」
5.共働き家庭の増加
6.経済成長戦略としての「小一の壁」の打破
7.就学をめぐる問題の構図の変化
8.「小一の壁」の社会的構築と見過ごされた問題
9.保護者を中心に据えたアプローチ
四章 小一の壁の実相――就労する保護者が抱える多様な困難
1.問題関心と研究目的
2.調査の概要
3.「小一の壁」の実相
4.学校からの時間的余裕のない求め
5.疲れを見せる子どもへの心配
6.先生や保護者との人間関係の疎遠化
7.結論
8.考察――余裕時間のない綱渡りの生活を強いられる家庭
五章 ひとり親世帯の保護者にとっての就学
1.はじめに
2.対象と方法
3.ひとり親が経験した就学前の準備と手続きについて
4.ひとり親世帯の保護者の相談相手について
5.ひとり親世帯の保護者の就労について
6.保育園と小学校の違いについて
7.考察――就学時のサポートとして必要な視点とは何か
六章 特別支援学級に就学した子どもを持つ保護者
1.はじめに
2.特別支援学級を就学先に選ぶ世帯の増加
3.先行研究
4.分析視点としての「生活世界の分化」
5.調査対象と方法
6.就学に関する長い語り
7.子どもの成育歴の中で経験された保護者の心配や困難
8.困難や不安の少ない就学
9.障害のある子どもを持つ保護者の生活世界
10.結論
七章 コロナ禍における就学
1.コロナ禍――非常時における学校教育と家庭
2.調査方法と調査対象
3.小学校等への就学と一斉休業
4.子どもの学校適応に関する保護者の不安や心配
5.勉強や宿題に関する不安・心配・不満
6.学校からの説明の不十分さ
7.就労する保護者が直面した困難や心配
8.非常時に見えてくる家庭と学校の関係
八章 学校選択制を敷くイギリスでの就学
1.問題の所在と研究の目的
2.先行研究
3.調査対象と方法
4.早期からの学校探索
5.段階的な移行のもとでの障壁の低さ
6.結果と考察
終章 保護者と子どもが安心して就学を迎えるために
1.四つの問いに対する知見のまとめ
2.「小一の壁」への対応策を再考する
3.就学により家庭に課せられる負荷
4.就学における様々な支援の存在
ほか
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
お抹茶