内容説明
コロナ禍での停滞を経てもなお、ライブミュージックは音楽文化や流行を力強く牽引し、現代社会のポピュラー音楽シーンでの存在感をますます増している。ライブミュージックをめぐる多角的な考察を通して、日本そして世界を覆う音楽文化の現在地を活写する。
目次
序 ライブミュージックの現況 南田勝也
第1部 ライブ文化の形成と展開
第1章 コンサート・パフォーマンスの歴史――クラシック音楽とポピュラー音楽の身体 宮本直美
1 コンサートの成立と展開
2 器楽の評価と「クラシック」音楽
3 沈黙する聴衆と身体抑制
4 ポピュラーなコンサート
5 ヴィルトゥオーゾへの熱狂――リストマニア
6 クラシックとポピュラー音楽をつなぐヴィルトゥオーゾコンサート
第2章 PA実践の文化史――循環器としてのサウンドシステムが生む「ライブ」な交歓 忠 聡太
1 二十世紀前半の電気的な補強
2 音量のさらなる補強と再帰的な回路の構築
3 シェイ=武道館史観を批判する
第3章 ライブパフォーマンスの半世紀――聴く/視るの二軸をもとに 南田勝也
1 デヴィッド・ボウイの挑戦
2 視ることが優先され、派手なパフォーマンスが繰り広げられた時代
3 同時代に日本では
4 化身や派手なパフォーマンスから撤退した時代
5 時代の転換を見据えて
第4章 巨大化するライブ産業――アメリカのライブ・フェスの現状 永井純一/山添南海子
1 巨大化する公演
2 「ライブミュージック」の台頭
3 パール・ジャムによる問題提起
4 コンサートの制度化と巨大化するプロモーター
5 ライブネーションによる水平統合
6 AEGによる垂直統合
第2部 それぞれの現場
第5章 ライブハウス店長の生活史――二〇一〇年代以降の「オルタナティブ」な場所作り 生井達也
1 「生」としてのミュージッキング
2 調査の概要
3 GLM店長のライフヒストリー
4 GLMの運営と店長の役割
5 地域との関わり
第6章 K―POPライブとファン――世代交代による進化と越境 吉光正絵
1 K―POPライブの現状
2 K―POPライブの特徴と変遷
3 日本の女性ファンが体験したK―POPライブの魅力
4 K―POPライブの行く末
第7章 3DCGライブの行方――初音ミクから考える音楽公演 南田勝也/木島由晶/永井純一/平石貴士
1 そこにいるはずがない人物に熱狂する観衆について
2 初音ミクのライブの何が新しかったのか
3 3DCGライブは現実を代替するか
第8章 推し活への唯物論的アプローチ――場所・モノから考える推し活のいま 阿部真大
1 推し活と場所――集合沸騰としての推し活
2 推し活とモノ――ファンが作る(使う)モノ/モノが作るファン
第9章 配信ライブの快楽と不満――メディアを介したライブ体験の行方 木島由晶
1 配信ライブとパンデミック
2 配信ライブの本格化
3 配信ライブの利用と満足
4 配信ライブの行方
終 章 ライブが存在感を増した社会背景――メディア、社会意識、共同体 南田勝也
1 レコーディング音源からライブ音像へ
2 コンサートからライブへ
3 「音楽になる」体験
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
無重力蜜柑
ぷほは
manabukimoto
じぇい
-

- 電子書籍
- 主人公と悪役の育成をしくじりました【タ…
-

- 電子書籍
- 半年だけのシンデレラ【分冊】 5巻 ハ…
-
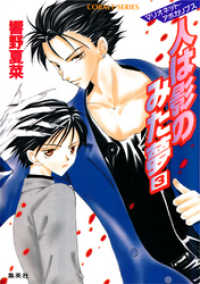
- 電子書籍
- マリオネット・アポカリプス 人は影のみ…
-
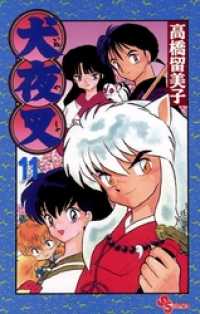
- 電子書籍
- 犬夜叉(11) 少年サンデーコミックス
-
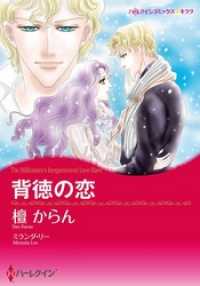
- 電子書籍
- 背徳の恋本編




