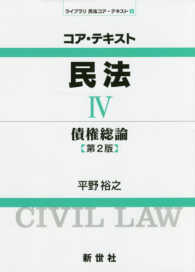内容説明
人々がSNSでつながり、AIが文章を生成する時代に、私たちはいかにことばと向き合っていくのだろう。ことばを紡いでいくたしかな技術を身につけ、自らの考えを自らの文章で伝えるための本。 【目次】第一章 曖昧なことばの感覚/第二章 これからの情報とメディアの在り方/第三章 5W1Hを捉えなおす/第四章 文の構造を理解する/第五章 文章の構造を理解する/第六章 究極の文章はとてもシンプルだ/第七章 なぜ文章を書くのか
目次
はじめに/第一章 曖昧なことばの感覚/「東」と「西」をどう説明するか/飛雄馬が見た、明け方の太陽と月/「南」と「北」は、「東の左右」で説明される/漢字に宿るストーリー/ストーリーへの共感が根拠に/科学的な視点で真実を知る/経験としてのストーリー/「やま」が出会った「山」という漢字/曖昧な「ことば」とどう付き合うか/インターネット時代のことば/「文章」は人にしか書けない/第二章 これからの情報とメディアの在り方/チャットことばとコミュニケーション/ヒト・モノ・コトを変化させる記号としての「情報」/人間は情報を求める生き物だ/情報を発信する手段としてのメディア/活版印刷と情報改革/メディアを担う媒体の変化/個人がメディアとなるときに求められるもの/第三章 5W1Hを捉えなおす/文と文章の定義/5W1Hでは文章はつくれない!? /4W1DにWHYを問いかける/WHYがもたらすストーリー/実生活にもつながるWHYの問い/WHYの使い方における誤解/「状況」「行動」「変化」を書く/第四章 文の構造を理解する/文構造のルール/主語と述語の関係を明確にする/一つの要素で一つの文を書く/助詞「は」と「が」の違いを知る/接続助詞と中止法はできるだけ使わない/無駄なことばを全部削る/わかりやすい文をつくれば必然的に文は短くなる/第五章 文章の構造を理解する/文章構造のルール/「骨」を書き、「肉」をつける/「肉」は「脈」でつなぐ──モンタージュ理論の応用/文章にも有効なモンタージュ理論/文で映像を生み、残像を次の文に ぐ/予測がもたらす書き手と読み手の齟齬/「起承転結」の呪縛/「前置き」は必要ない/「結論」は必要ない/第六章 究極の文章はとてもシンプルだ/答えはいまだに出ていない/あなたのエピソードを書くということ/無駄なことばを削ることは必要なことばを残すこと/書くなら肉まんよりミルフィーユにしよう/文章は高級ブランド店よりコンビニの棚を目指せ/伝統的に抱えた「心理的共感」の壁/最後の一文は削ろう/第七章 なぜ文章を書くのか/文章と文書の違い/生成AIで文章は簡単に書けてしまう? /文章を書いているはずが文書になっている/「好きなことを書けばいい」ってどういうこと? /書くことは文通から始まった/必要なのはアウトプットだった/自分自身の「時」を記す/時の力を借りて、自らの「芯」を明らかにする/思考の軌跡=ストーリーを書く/おわりに
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
よっち
takka@ゲーム×読書×映画×音楽
tharaud
vodka
rukaq
-

- 電子書籍
- 【単話版】魔法医レクスの変態カルテ 第…
-

- 電子書籍
- Scratchで楽しむ レッツ!プログ…