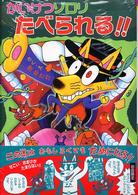- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
「すべて自分が悪い」というふうに自分の存在を否定することで、世界の合理性を獲得する。この感覚を、自責感といいます。臨床心理学では、自責の問題はほとんど扱われてきませんでした。この本では当事者の言葉を辞書として、自責感だけでなく、母と娘、共依存、育児といったものにまつわる問題を考えていきます。講座の語り口を活かした、やさしい一冊です。
目次
まえがき/第1章 母はまだ重い/1 「母と娘」の時代の幕開け/精神分析のなかの女/フェミニスト・カウンセリング/アダルト・チルドレン/被害という概念の広がり/『母が重くてたまらない』へ/2 母と娘のいま/母娘問題のはじまり/毒母、毒親という言葉/母の老い/自分の限界は甘く見積もる/亡くなった親/3 母を俯瞰する/定義にこめたもの/母親の三大原因説/謝罪になっていない謝罪/母と娘は和解できない/4 グループの力/解釈を一切しない/母親研究/言いっぱなし・聞きっぱなし/生育歴が母親研究になる/母を俯瞰する/不均衡な力関係の表れ方/第2章 共依存を読みとく/1 共依存とシステム家族論/当事者の言葉/アルコール依存症の治療現場から/システム家族論の登場/システム家族論の影響/2 支配としての共依存/共依存の発展/従来の共依存理解の限界/依存ではなく支配/「あなたのために」が不幸のはじまり/言葉が現実をつくる/母の愛のいかがわしさ/被害者権力/パターナリズム/3 母と娘の共依存/母のケアが力を奪う/あなたがいないと生きていけない/女性と共依存/共依存的な人にどう対処するか/共依存的になってしまうとき/被害者は無力化されているのではない/権力は状況の定義権/支配の根幹/4 複雑化したトラウマ/苦しみと鈍感さ/ありふれている共依存/支配性を自覚する/第3章 母への罪悪感と自責感/1 近代と母性愛/母と娘に関する3冊/罪悪感の正体/つくられた家族像/母性愛のふたつの柱/2 母のミソジニー/精神分析にとって女とは何か/阿闍世コンプレックス/受け継がれる母性信仰/ミソジニー/3 母性愛と罪悪感・自責感/反出生主義/虐待の影響としての自責感/母性愛なんてものはない/4 第三者の介入/最良の第三者は、父であるべき/キーワードの整理/第4章 逆算の育児/1 子どもとは何か/アルコール依存症とフェミニズムの合流/90年代のはじめの孤立/ACの親のように、じゃない育児/子どもという存在/2 親の言葉による支配/親の暴言/自立という言葉/人に迷惑をかけずに生きることはできない/家族と差別/加害と被害をひっくり返す/普遍的な価値を利用する支配/3 幸せでいる義務/抑圧移譲/強迫的なケア/子どもの前では幸せでいる義務がある/閉ざされた家族/幸せなふりをする/4 とりかえしはつく/子どもの恐怖/子ども以外の存在から支えられること/子どもが許せない気持ち/とりかえしがつかないことはない/第5章 なぜ人は自分を責めてしまうのか/1 自責感と規範の関係/規範を取り込む/規範の一貫性/2 「すべて自分が悪い」という合理性/感情を抱けない/子どもの文脈/たったひとつの合理性/3 根源的受動性/子どもは責任ゼロで生まれてくる/孤独感は高級な感覚/虐待の罪/4 自責感のあらわれ/自傷はサバイバル/アディクション/摂食障害/性的な問題/反転する自責感/家族と正義/あなたは悪くない/5 これからの旅へ/グループの意味/ヴィクティム・ジャーニー/あとがき/索引
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ネギっ子gen
たまきら
こばまり
olive
mimiii
-

- 電子書籍
- マッチングアプリで嘘をついたら~向井地…