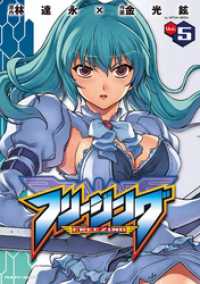内容説明
「歴史的事実」とされるものは何か? 科学哲学・分析哲学の立場から,「歴史の物語り論」「歴史修正主義」など歴史認識の問題を七日間の講義という形式で,わかりやすく解説する.現代文庫版では,「補講」として歴史学者・遅塚忠躬の本書に対する批判についての反批判も収録.人文科学のあり方を問い直す知的刺激に満ちた本.
目次
第1日 歴史哲学と科学哲学
第2日 歴史認識をめぐる論争
第3日 出来事としての歴史/記述としての歴史
第4日 歴史における説明と理解
第5日 歴史の物語り論(ナラトロジー)
第6日 過去の実在
第7日 歴史記述の「論理」と「倫理」
補講1 過去の実在・再考
補講2 「歴史の物語り論」のための弁明
参考文献一覧
あとがき
岩波現代文庫版へのあとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
gorgeanalogue
15
大変分かりやすかった。補講の「弁明」も面白い。「歴史修正主義」に向けての「弁明」がこの本が書かれた動機なんだろうとは思うものの、物語とか実証主義、とかの用語の歴史的なリアリティから(それこそ「曖昧な言語による構成」ゆえに)自由になることはできないだろうから、これで決着がついたことには到底ならないに違いない。一方で素朴に、この立場では写真とか映像をどう考えるのかな。その時「想起」はどう位置づけられるのか。ベンヤミン論が含まれているはずの『物語の哲学』を読みたい。2024/08/23
ころこ
15
我々にとって意味や価値とは一体何なのか。解釈学→現象学、特にフッサールにおける『志向的構成』という考え方に依拠して、歴史を語るという行為を考察している本です。『語り口』は平易なものの、ピンとこないと難解に感じるかも知れません。解釈学というと、筒井康隆「唯野教授」を思い出しますが、分析哲学からの問題意識だというのは、冒頭の意味や価値の探究だということからも分かります。歴史が『語り』になってしまうのは、超越的な視点を持ちえないため、客観性をも持ちえない。さらに過去の出来事は知覚できない。我々は歴史の内部(一部2018/01/14
ネムル
14
科学哲学の側から、歴史を物語る倫理より論理が主に考察される。そこにやや不満を感じもしたが、歴史の歪みを補正するのでなく、公共化された記述の歪みを自覚・分析するための、土台作りとし読む。繰り返し描かれる時間のアナロジーがどこまで妥当か、いまだ語られず公共化されない歴史がどれ程あるか疑問はつきないが、まずはここから。2019/05/17
かんがく
12
講義形式で語り口はやさしいが、扱われる内容は極めて難解。過去を研究する歴史学の営みに対して、「過去」とは、「事実」とは、「理解」とは、と哲学的な問いをぶつけていきまくるムキムキな本だった。ある程度歴史学に関する本を読んだことがあったので、なんとなく議論についていくことはできたが、頁数は少ないためやや物足りない印象だった。2024/11/23
武井 康則
10
1980年代以降、歴史学の領域で「言語論的転回」が叫ばれるようになり、歴史的事実の客観性をめぐっての論争が繰り広げられたそうだ。著者は本来、その科学が認められるかを問う科学哲学者だが、今回対象がすでにない歴史においてどうすれば歴史学が成り立つかを問う。答えとして物語る(ナラティブ)ということ。フィクションでなく、言語で語るということ。言語である限り因果論に縛られ、その整合性が批判され続けることで成り立つとする。フッサール、分析哲学、ポパーなどに依拠しつつ、架空の集中講義で前提から結論まで丁寧に語っていく 2025/12/19