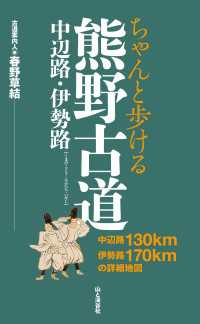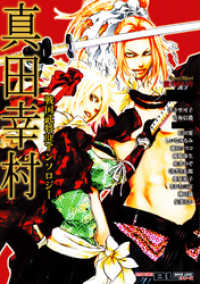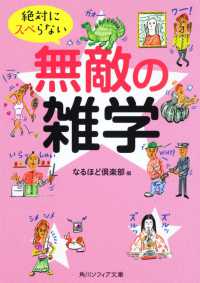内容説明
子どもたちの学びの多様性を尊重することがなぜ大切なのか。ニューロダイバーシティの第一人者による教育システムへの新たな提言。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ta_chanko
18
明治維新から150年。欧米列強にキャッチアップして急速な近代化を目指す政府にとって、子どもたちに一斉授業で知識を教える学校制度は効率的だった。しかしVUCAと呼ばれる先行きの見えない予測困難な時代にあっては、教育制度も変わっていかなければならない。子どもたちにとっても、規格化・平均化を求められ、外れると学習障害・発達障害にされるよりも、多様な学びを自ら選択することで個別最適な学びを見つけていくほうがはるかに主体的・意欲的になれる。学校も試行錯誤を重ねながら、最適な学びを追究していくべき。2024/10/17
つかさ
4
個別最適で協同的な学びについて勉強したくてこの本を買いました。多様な学びができるような学校になれば、先生も生徒も毎日がもっと楽しくなるのではないか、と思いながら読んでいます。2024/08/20
hana✻マインドサポーター✻
3
ラーニングダイバーシティの考え方で教育を実践できれば、特別支援教育も、ギフテッドも、不登校もすべて丸く収まるんじゃないかと思った。学校を絶対的な存在にせず、「一つの選択肢」として、誰もが学びやすい環境が整備されることを願う。2025/07/17
Mituya Hasegawa
3
バタバタとしていて読み進めるのに時間がかかりましたが、多様な学びの理解を深めるには読むべき一冊です。📖 2024/12/05
つかさ
3
配慮ではなく「アコモデーション(近いニュアンスは「調整」)」が必要という言葉はしっくりきた。私はどうも配慮という言葉を聞くと、気を配ってできるようにしてあげなければいけないという気持ちになってしまうから。この気持ちはなんというか偉そうで、傲慢だなと。何様よ、私…と思っていたので「調整」の方が言葉が好きだ。 唯一絶対の正しい学び方があるのではなく、それぞれの特性にあった学び方があるのだから、学校はその学び方を色々試せる場であってほしいと思う。2024/11/29