内容説明
インドのしたたかさは古代からあった!
紀元前2~4世紀の古代インド、マウリヤ王朝の宰相カウティリヤが著わしたとされる『実利論(アルタシャーストラ)』。マックス・ウェーバーが『職業としての政治』のなかで「カウティリヤの『実利論』に比べれば、マキャヴェリの『君主論』などたわいのないものである」と評した、冷徹なリアリズムにもとづく国家統治の要諦を論じた幻の書だ。
その白眉は「マンダラ外交」と呼ばれる外交論。自国に直接境界を接する隣国は基本的に「敵対者」、隣国の隣国は友邦になり得る国、そのまた隣国は敵対者となり得る……という具合に円環状に広がって行く外交戦略論だ。
単に「敵の敵は味方」と言うに止まらず、自国と敵対的な隣国の双方に接する「中間国」、また自国にも隣国にも接しない「中立国」を活用することの重要性とさまざまなケースでの対応策を提示。採るべき政策として、和平、戦争、静止、進軍、依投(他に寄る辺を求めること)、二重政策(和平と戦争を臨機応変に採用すること)という「六計」を、状況に応じて繰り出していくとする。これは現代インドにおいても当てはまる。
その他、日本がまだ弥生時代の頃に、驚くほど緻密な官僚制を敷き、インテリジェンスなかでもスパイの効用をさまざまに論じている『実利論』を、筆者が兵法の古典『孫子』との比較や、ガンディー、ネルー、チャンドラ・ボース、あるいは現モディ政権のジャイシャンカル外相らの政治・外交を紐解きながら、現代インドの行動原理と併せ解説する。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
とり
4
古代インドの政治論書「実利論」を現代の視点から解説している。帝王学、外交、兵学など扱う範囲が広く、マウリヤ朝時代の古代インドの価値観がわかって興味深い。マックス・ウェーバーによれば、「カウティリヤの『実利論』に比べればマキャヴェリの『君主論』などたわいのないものである」とのことだが、確かに実利論は君主論以上に非常に冷徹。2025/05/04
Shinya Fukuda
2
第一章では実利論誕生の背景が書かれている。第二章では内政や司法制度について書かれている。第三章では外交について書かれている。第四章では諜報活動について書かれている。王が国を統治する際に必要とされる内政、外交、諜報について緻密に論議が進められる。第五章では孫子の兵法との類似点、相違点が書かれている。第六章では現代インドで実利論が如何に活用されてきたのかが書かれている。第六章では日本は実利論から何を学べるのかが書かれている。実利論の特長は徹底したリアリズムである。これは幾ら強調してもし過ぎることはないだろう。2025/11/30
於千代
1
古代インド・マウリヤ朝の政治書を紹介しつつ、それに基づいてインド近代史を読み解く一冊。恥ずかしながら種本の存在を初めて知り、興味深く読み進めた。『孫子』との共通点もあり、時代や地域を超えて戦術論には普遍的な要素があるのだと感じた。2025/05/24
tetsuwo
1
「実利」は自明なようでそうではない。有能な戦略家でもなければ、手段を目的化して実利を見失うことはよく起こるだろう。実利を取るためには徹底したリアリストであることが必要と述べられる。1つの価値基準(例えば実利)を軸に手段を評価することができ、基準に沿わないものをためらわずに捨てる覚悟を持つ人だ。現実を、諦める理由にするのではなく、解決策を見つけるための分析対象にしていかなければならない。2025/04/27
Go Extreme
1
実利論:カウティリヤ 統治原則 政治戦略 経済政策 外交戦略 情報戦 戦争戦略 権力維持 マンダラ理論 国家運営 法制度 司法制度 社会安定 行政監視 統治技術 インテリジェンス:スパイ活動 情報収集 諜報戦術 懐柔策 離間策 牽制策 武力行使 心理戦 国家安全保障 戦略的判断 内部監視 秘密工作 外交政策:マンダラ外交 非同盟運動 国際関係 戦略的提携 近隣諸国対応 外交均衡 軍事同盟 貿易交渉 経済協力 交渉術 国家統治:指導者の資質 官僚制 経済発展 秩序維持 施策実行 民衆統制 国家防衛 社会制度2025/03/11
-
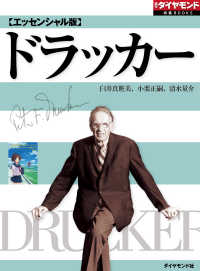
- 電子書籍
- 【エッセンシャル版】ドラッカー - (…





