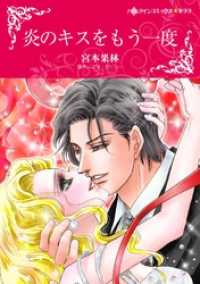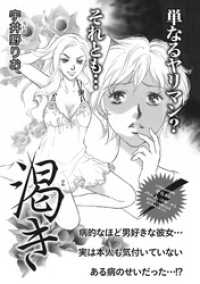- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
例えば、ベストセラー作家の曲亭(滝沢)馬琴は、誰と、どんなやり取りをしていたか。手紙だけでない飛脚が運ぶ物産、飛脚問屋の金融的な機能や全国津々浦々の情報流通に果たした役割とは。自然災害や事故、強盗等の被害にどう備えていたか。近代郵便制度の導入以前でも、全国につながる街道、江戸市中に張り巡らされた飛脚ネットワークは相当にすぐれていた。飛脚の成り立ち、制度の変遷、ビジネス化成功の裏話、やり取りされた手紙の内容まで、江戸時代の輸送の全貌を解き明かす。
目次
はじめに 死語にならない「飛脚」/第1章 馬琴の通信世界/馬琴の飛脚利用/大坂の板元とのやり取り/校合作業と刊行/頻繁な馬琴の飛脚利用/荷物到着日数/荷物の中身と状態/第2章 「飛脚」の誕生/1 飛脚と源平合戦 “馬”は足の延長/「飛脚」の語の淵源/飛脚のなり手──雑色が活躍/2 戦国時代の飛脚 足利義輝の「早道馬」構想/三つの通信手段──使者、使僧、飛脚/武田氏の飛脚/今川氏の飛脚/真田氏の飛脚/第3章 三都の飛脚問屋の誕生と発展──ビジネス化した飛脚業/江戸時代とは/商業経済の沸騰/江戸がゴール/京都順番飛脚仲間の誕生/越後屋孫兵衛──三井の飛脚問屋/大坂三度飛脚仲間/江戸定飛脚仲間/十七屋孫兵衛の発展/早飛脚の誕生/第4章 飛脚問屋と出店、取次所/1 京屋弥兵衛 輸送ネットワーク/京屋甲府店/上州の京屋──桐生店・高崎店・藤岡店/奥羽の京屋──福島店・山形店・仙台店/2 嶋屋佐右衛門 嶋屋江戸店/上州の嶋屋──桐生店・高崎店・藤岡店・伊勢崎店/北国、奥羽、蝦夷の嶋屋──水原店・新潟店・福島店・山形店・仙台店・箱館店/3 飛脚取次所 五街道の取次所と業務/脇往還の取次所/第5章 飛脚輸送と飛脚賃/馬琴宅から嶋屋までの距離/馬琴、嶋屋を使う/並便──廉価な定期便/早便──時間を金で買う速達便/抜状との併用──延着防止のカギ/「上方・下方抜状早遅調」──飛脚の時刻表/仕立便──一通のための超特急便/第6章 奉公人、宰領飛脚、走り飛脚/店奉公人──荷物を受注/宰領飛脚の所持品/宰領の情報網/走り飛脚は速さより安全優先/飛脚の走り方/走りの職人/第7章 金融と金飛脚/1 織物購入資金をプール 絹市の現金──松原の渡し難船事故/難船の原因/預り金手形/2 為替手形 便利な手形/京都と織物取引/為替手形の弱点/3 融資 融資の対応/飛脚問屋の金融とは/第8章 さまざまな飛脚/1 武家専用の飛脚 幕府継飛脚/七里飛脚/大名飛脚(藩飛脚)/2 多様社会の飛脚 チリンチリンの町飛脚/立花屋の輸送網と飛脚賃/川崎宿に町飛脚創業/大名行列で活躍した上下飛脚屋/3 二見屋忠兵衛──飛脚取次の商人 馬琴と牧之の交流/二見屋忠兵衛の正体は? /死蔵される『北越雪譜』/4 人足社会の江戸 馬琴の使った人足──日雇人足太兵衛/御用松茸献上の人足/5 「使」担う奉公人 滝沢家の「むら」という女性/村と村をつなぐ定使──廻状を運ぶ/処罰としての定使/第9章 飛脚は何を、どうやって運んだか/1 大名の生活資金を運ぶ 紀伊徳川家の御用送金──伊勢松坂、山城屋市右衛門/尾張徳川家の京都・大坂輸送──井野口屋半左衛門/井野口屋の輸送路/商人荷物/2 特産物の輸送 奥州福島の生糸輸送/出羽最上地方、紅花取引での利用例/3 特殊な飛脚利用 「播磨の飛脚はまだか?」──新選組/内緒のお荷物もお届けします/第10章 災害情報の発信/1 火災情報 刷り物で配布/日記に写された火災情報/京都で伝達された江戸大火/2 天災情報 大地震を伝える/洪水情報/3 戦争情報 江戸薩摩藩邸焼き討ち/鳥羽伏見戦争の第一報/戦争直前、上野に屯集/4 飛脚問屋はどう伝えたのか 情報伝達は顧客サービス/江戸のメディア/第11章 飛脚の遭難/延着の原因/水難事故/盗賊の標的/荷物の賠償問題/輸送当事者の弁済/延着でも利点/第12章 飛躍する飛脚イメージ/1 文学・芝居の飛脚 史実の「冥途の飛脚」/梅川の後日譚/歌舞伎「恋飛脚大和往来」/歌舞伎「御存鈴ヶ森」/2 黄表紙の中の飛脚 山東京伝『奇事中洲話』/山東京伝『早道節用守』/竹の塚の翁『雲飛脚二代羽衣』/3 俳諧・川柳の飛脚 俳諧に点描される/ユーモラスな川柳の飛脚/狂歌に詠まれる飛脚/4 話芸の中の飛脚 明石飛脚/堺飛脚/5 狐飛脚伝説 狐の使い/出羽国の与次郎狐/右近・左近の狐飛脚/各地の狐飛脚伝説/6 伝説所在地 南北と蕪村の狐飛脚/日本海側に多い狐飛脚/本書まとめにかえて/あとがき/参考文献/巻末資料/滝沢馬琴の飛脚問屋利用(文政10年─天保11年)/武田氏関連史料中の「飛脚」一覧/今川氏関連史料中の「飛脚」一覧/真田氏関連史料中の「飛脚」一覧/文化3年(1806)4月、定飛脚仲間問屋六軒仲間、飛脚賃/滝沢馬琴と鈴木牧之との書翰往復(文政10年─天保5年)/馬琴の日雇人足利用(文政11年─天保4年)/上野国甘楽郡譲原村「歩行役」使用数(安永4年〈1775〉)/山城屋、御用送金回数と合計額/井野口屋が無賃で請け負った主な尾張徳川家御用荷物/大橋儀左衛門、生糸商大橋家依頼荷物一覧表〈嶋屋福島店請負〉/飛脚問屋扱いの堀米四郎兵衛宛て紅花代金受取〈文政5年─天保6年〉/宮川家文書所収の飛脚問屋運送事故関連史料一覧
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
よっち
まー
アメヲトコ
いざなぎのみこと