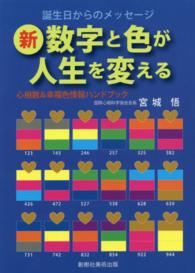内容説明
ウクライナ侵攻とガザ情勢の悪化以降、国連は機能不全に陥っている。国連は現在どうなっているのか。冷静沈着に国連の役割と限界を見据え、いま何ができるかを考えることが重要である。外交官として国連日本代表部に二度勤務した著者と、長年にわたり国連の理論的研究に携わってきた著者の二人が、現場での実務経験を縦糸に、研究者の体系的な理解と分析を横糸にして、国連の実像に迫る。初学者にも、学びなおす人にも、最先端の情勢と研究を知るために有益な画期的入門書。
目次
はじめに/序章 国連の現在──機能不全のなかで/終わりの見えない二つの“戦争”/問われる国連の存在意義/「国連」とは/「平和」とは/本書の問題意識/第1章 国連誕生──歴史を振り返る/第二次世界大戦の教訓と国連の誕生/ダンバートン・オークス会議からサンフランシスコ会議へ/機構構想をめぐる対立の萌芽/国際連盟の教訓と国連の目指すもの/国際社会の成立と国際機構/国際社会の組織化の変遷/国際機構誕生の法則/主権国家の制御とカントの平和構想/ヨーロッパ協調とハーグ会議/国際連盟はなぜ第二次大戦を防げなかったのか/第2章 国連の描く平和と安全保障構想/戦後の世界秩序構想としての国連/武力行使の禁止と集団安全保障/安保理の拒否権とは何か/冷戦のはじまりと国連に落とした影/安保理の機能麻痺と「平和のための結集決議」/冷戦期の安保理の動き/スエズ紛争とPKOの誕生/植民地の独立と総会の台頭/国連事務総長とICJの役割/冷戦後の安保理と問われる平和のかたち/民族紛争の頻発と変化するPKO/人道的介入と保護する責任/人権の主流化/第3章 国連の現場から(1)──冷戦崩壊後、一九九二~一九九五年/冷戦の崩壊と国連/平和への課題/安全保障理事会とはどういう所/国連代表部の一日/ソマリアへの介入/ルワンダ大虐殺/自衛隊派遣/モザンビークPKOへ/第6委員会とは/「国連要員安全条約」の制定へ/ローマ規程から国際刑事裁判所の創設/第4章 国連の現場から(2)──9・11後、二〇〇一~二〇〇三年/9・11に遭遇/大島賢三事務次長の奮闘/人間の安全保障と人道的介入/イラク侵攻に備える/国連と人権/人権決議の採択を主導する/クメール・ルージュ裁判/舞台はニューヨークへ/いよいよ決議案採択へ/国連の選挙とは/第5章 北朝鮮の核・ミサイル開発と国連/日本の終戦と朝鮮の解放/冷戦から熱戦へ・民族同士の殺戮/朝鮮問題と国連、そして南北国連同時加盟へ/第一次核危機・国連安保理の最前線で/苦難の行軍と国連による人道支援/核・ミサイル開発と制裁、負のスパイラルへ/制裁の効果と限界/国連事務総長の役割/ロシアと北朝鮮の急接近、制裁は崩壊するのか? /第6章 ミャンマーと国連──クーデター以降/クーデター発生/ASEANの取り組み──議長国ブルネイで奔走する/ASEAN特使の任命とエルワン特使の苦悩/安保理と総会の行動/国連特使の努力/人道危機と国連の支援活動/対立が激化する現場/打開が見いだせない国際社会、国連の役割は? /第7章 国連改革の行方/国連改革と安保理改革/改革論議の経緯/安保理の何が問題なのか/安保理改革の具体案/ウクライナ戦争の経緯と国連の対応/イスラエル・ガザ紛争の経緯と国連の対応/総会による説明責任の試み/分かれる国連観/世界政府か国連か──カントの平和構想/第8章 国連の課題と未来への展望──改革の三つの方向性/『平和への課題』と平和構築/アナン報告と平和構築委員会/国連の民主化とNGO・市民社会の参画/国連のパートナーシップ/機能不全の本質/戦争の実相と包括的な平和への取り組み/人間の安全保障/SDGs、そしてグテーレス事務総長の呼びかけ/よりよき世界への処方箋と私たちの役割/終章 国連改革に向けて日本に求められるもの/待ったなしの安保理改革/現実的目標設定の必要性/拒否権をどう抑制するか/おわりに/参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ベンアル
スプリント
FFLJAPANter
お抹茶
Go Extreme
-

- 和書
- 西遊記 〈1〉 岩波文庫