内容説明
同じ水頭症の障害をもって生まれながら、療育→特別支援教育の“障害児専用コース”を突き進んだ長女と、ゼロ歳から保育園、校区の小・中学校学に学ぶ長男。二種類の“義務教育”を保護者として経験した辿りついた結論は。障害のある人を「私たちとは違う環境でないと生きていけない人たち」と場を分け、交じわる可能性を摘むことこそ差別であることを、2人の子どもの成長とともに親が気付き、自己変革をとげていく過程を描いた痛快エッセイ!
【主な目次】
はじめに~「彼ら」と「私たち」
第一章 子育てと介助・介護を仕分けする~母親元年
一 シャバに助けを求める
二 「介護・介助」と「子育て」を仕分ける
三 「圧倒的な共感力」の中で暮らし始める
第二章 二十年後の自分に会う~母であるより友人として
一 これを教育といえるか
二 共に生きる決意の頃(社会も私たち家族も)
三 これは彼の意思
第三章 バリエーションはすべてを可能にする~保障すべきもの
一 インクルーシブを体感する
二 排除、排除、排除!
三 等しい人権をもつ人間として
第四章 絶望のさなかの希望~「死んでいい人」のかごに入れられて
一 絶望の後、浮かび上がった道
二 バリエーションは、この世界を救う
あとがき~猿が、木から、落ちた
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
のみちゃん
2
以前からの「障害者隔離施設は要らない。異常なコミュニティは解体すべきだ」という思いを、より強くすることができた。現在は休止中ということだが、ポルトドスの活動をバリアフリーやユニバーサルデザインを考える有志と共に行うことによって、人も社会も成長できるに違いない。活動が広くなれば、一般の目に触れる身近な活動となるだろう。作業のための作業所を解体して欲しい。隔離されてしまっている当事者にしかできない活躍はあるのだ。ただ、全面的に著者に協同できるかというと違う。後世に優性であって欲しいという思いは変わらない。2016/06/30
ちい
1
「インクルージョン」という言葉を知ったのは、聴覚障害者を支援する勉強を始めた頃だったか。それ以来、幾度かこの言葉を耳にするけれど、分かったことは、社会は簡単には変わらないのだということ。当事者が声を上げ続けないと、変わらないものなのかしら。まずは、知る事が大事で、知るためには隔離してちゃダメだよね。2017/03/12
くろすけ
0
療育に関わる職種、特別支援学校・学級の教員が読んだら、あるいは療育が必要だと思っている親、特別支援学校・学級に子供を入れることを選んだ親が読むと胸が騒つく本です。 ただ、著者の最も主張したいことは、命にはバリエーションがあり一人一人が完璧で自由な存在だということ。誰にも強制されず、自分の選んだ人生を歩める権利を持ち、それが当たり前の社会であることを望むということだと理解しました。 共感できます。2017/11/04
-

- 電子書籍
- HP1で無双【タテヨミ】15話
-

- 電子書籍
- すべてを奪われた王女は騎士を待つ 第2…
-

- 電子書籍
- 水と緑と土 改版 中公新書
-
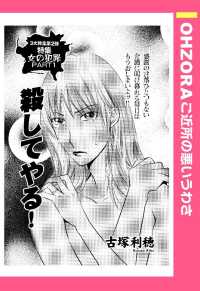
- 電子書籍
- 殺してやる! 【単話売】 - 本編 O…
-
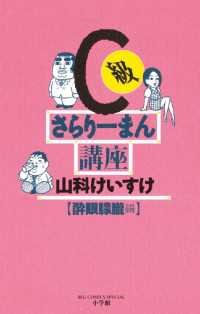
- 電子書籍
- C級さらりーまん講座(9) ビッグコミ…




