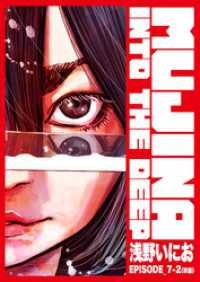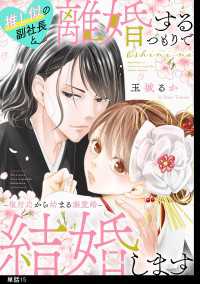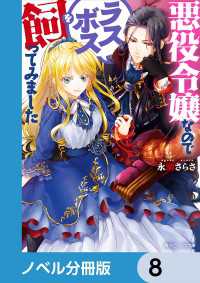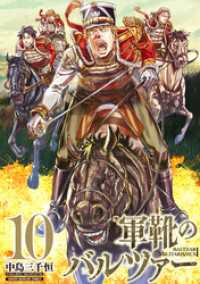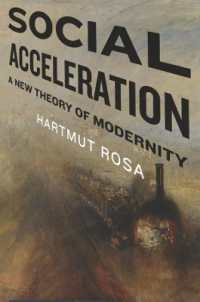内容説明
名古屋という都市を論じる書の決定版!
名古屋をテーマにしながら、単なるご当地本ではない、非常に大きなスケールで名古屋が論じられ検討されている。
ういろう? 味噌カツ? シャチホコ? 名古屋城? よそ者に閉鎖的? 名古屋といえばこんなイメージだが、こういったブツやらなにやらのイメージからあえてはなれ、現代思想を道具として用い、名古屋という都市の形成過程を歴史的に追うことで、名古屋という都市空間の一般的な性格を導き出す。
改めて、名古屋、ひいては都市一般を考える上で必須の一冊。
【主な目次】
第一章 1918 鶴舞
第二章 1965 小牧
第三章 1989 世界デザイン博覧会
参考文献
あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
えも
14
浮かれた名古屋のあるある本だとばかり思って借りたら、全然違って、名古屋の都市計画や周辺の開発を批判的に論じた書だった。副題の「ユートピア空間の形成史」も、名古屋をいわばディストピアと断じている内容からして、皮肉が効いている▼ただ、「商人資本によって人と物と情報が集積する東京や大阪を大都市というなら、名古屋は都市ではなく、工業地帯の結節点の一つに過ぎない」なんてのは小気味いいし、「広いだけの道路は空虚で、都市には混沌とした狭い路地が必要」との主張には激しく賛成!2019/10/15
Mealla0v0
8
なぜ名古屋がつまらない街になったかを滔々と語る本。都市計画、モータリゼーション、ジェントリフィケーション。これらは都市が元来持つエネルギーを根こそぎにしていく方法であった。大正期には米騒動に始まり労働運動がうねりを上げて行くが、これをどうにか破断させるために都市計画が持ち上がる。地主を利害関係者にし、軍需産業の勃興に伴う労働者の分断が生ずる。次いで自動車の到来は道幅の拡張を呼び、それは人間スケールの街の破壊だった。最後に新自由主義による都市の掃討、つまり都市のごみごみとした感じをクリーンにする戦術。2021/11/24
臓物ちゃん
7
何ィ〜名古屋に意味もなく100メートル道路が2本もあるのはヒトラーの仕業だというのかァ〜!?そんな感じで如何にして自動車と工場と名古屋走りが君臨する異形の都市が誕生したのかを20世紀を通して解明した、負の名古屋観光案内本。中京デトロイト化構想、名古屋大空襲、大須事件、小牧基地拡張、世界デザイン博覧会……といった具合に地方性とファシズムの奔流がどんどん今の名古屋を形作っていく歴史は都市論好きの俺にはたまんねぇ面白さ。「もうやめましょう…!名古屋について考えるのは…!」とハンチョウでなくとも言いたくなる一冊。2022/08/08
晩鳥
3
名古屋が好きではない著者による、主に都市計画の面から名古屋を批判した本。「名古屋は東京・大阪のような商人都市ではなく、工業地帯の結節点」「100m道路に代表される名古屋の都市計画は人間の尺度を失っている」など納得する主張も多い。名古屋に比べると岐阜はおしゃれ、「岐阜モダニズム」と呼べるものがあるとは、そういう見方もあるのか。著者の名古屋は人間性を失った産業都市であるという意見は同意する点もある一方で、高度に計画された都市はそれはそれで面白く、また違う魅力もあるとは思う。2025/06/08
toshi
3
この本は名古屋を舞台にした地理学の本である。対象は都市であり、方法は歴史学である。特に労働/大衆運動史、産業史、都市計画史から、「名古屋がつまらない理由」を明らかにしている。また都市の荒廃の未来を名古屋から見ている。その荒廃は人間の知覚を変容させるとしている。都市社会学のタームであるイゾトピーとヘトロトピーの紹介から、私は都市の街歩きが好きであるが、名古屋はどこを歩いていいのかわからないと感じた理由が、イゾトピーの解説でよくわかった。詳しくは本書に読んでいただきたい。2019/07/20