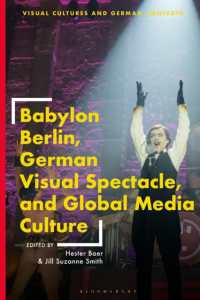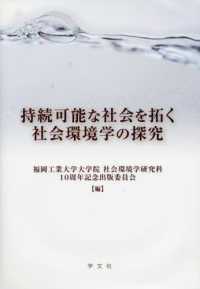内容説明
『A3』から約5年。森達也氏が、元オウム真理教の信者で麻原彰晃に帰依していた夫婦との対話を通して新角度からオウムを照射! 巻末にマンチェスター大学日本学シニア教授で、「メディアと新宗教の相互作用の研究」をしているエリカ・バッフェリ教授の解説付。麻原彰晃の死刑執行が囁かれている今、見過ごされてきた真実が次々と明らかに。
【主な目次】
1 オウム真理教との出会い
2 出家者の生活
3 麻原彰晃の実像とは
4 オウム真理教事件
5 いま、振り返るオウム真理教
結びとして 宗教リテラシーからオウムを考える
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
hk
17
森達也氏とオウムの元中堅幹部2人による鼎談集。甚だ違和感が残る内容だ。というのも元中堅幹部のセリフは専門用語がてんこ盛りであり、市井の人々に伝えようという熱意が感じられないからだ。「この人達はやはり特殊なんだ」と思ってしまったのは私だけだろうか?森氏もそれを咎めたり注釈を入れないのは頂けない。オウムを取材しているうちにその集合的無意識に染まってしまったのだろうか。ジャーナリズムとは伝えることが至上の任務だ。伝わらない言葉では世の中は変えられないよ。これではオウムがやったことの二の舞ではないだろろうか。2018/06/06
pia
9
元信者のお二人と、森さんの対談。流石に4作目ともなると、森さんの同じ主張の繰り返しで新しさは無い。深山さん、早坂さんのお二人は彼らなりの筋の通った主張をされているように見えたのだけど(共感できるかどうかはともかくとして)、森さんが「ちょっと待って、それは理解できない」という話の止め方をするのが非常に気になった。「そういう考え方もする人がいる」事実が全てじゃないの?そうやって共感されにくい意見を「理解できない」と否定してしまう事と、森さんがいつも批判していたメディアがやってる事との違いはどこにあるんだろう。2021/01/24
すん
9
本で対談をしている早坂さんの、麻原とオウムを前にして日本社会は心をかき乱されて自分たちでつくったはずのルールを守れなくなったように見える、という言葉が印象的だった。心神喪失者を裁判にかける。麻原の子供に対して義務教育を拒否する。信者の住民票を受け取らない。いざとなると社会で憲法違反を行い、それに対して無自覚であることが証明されてしまった。であれば、少しでもましな人間になるためにどうすればよいか。どのような行動をとることが自分に恥じないのか。心の拠り所となる宗教を持たない人達こそ、よく考え行動する必要がある2019/02/21
imagine
8
渾身の作品『A3』に比べてずいぶん気前良くついた『A4』のタイトルは、悩んだ末に著書が冠したとのこと。元信者の二人に教団の生活やサリン事件当時の話を聞き、『A3』での仮説も検証してゆく内容。オウムの教義と完全に決別したわけではない元信者二人の回答は、どこか未練がましい。あまりに常識を逸脱するとさすがに著者が突っ込む(笑)。サリン事件については事態が予測できれば協力しなかった、と悪の凡庸さを露呈。服従(忖度)の構造が立ち上がる。オウムにおいてのミルグラムはまだ現れないと指摘する著書こそが、まさにその人では。2019/07/03
むっちょむ
6
麻原さんが死刑になってからオウムの人達がなぜあんな事件を起こしたか、気になって仕方なくて何冊か読んだうちの1冊。読んだ感想としては、オウムの信者さんは、いわばお坊さんのよう、ほんとに修行者だったんだなと。ときどき、その発想は独特すぎてついていけない。。きっと被害者の方が読んだらかなり不快なのでは?!と思う記述も何度があった。ただあの時代オウムが必要な人たちもなりいたわけで、そこを私たちは特殊な人達だけがハマった宗教と、捕らえていてはまた同じことを繰り返すと思った。2018/08/26