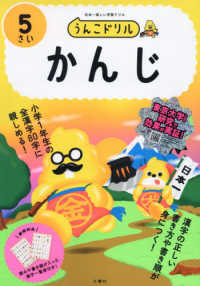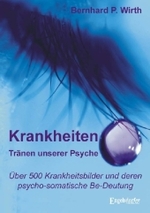- ホーム
- > 電子書籍
- > 趣味・生活(スポーツ/アウトドア)
内容説明
時代遅れの指導はなぜなくならないのか?
ベストセラー「<叱る依存>がとまらない」の著者が質す
子どもたちの学びや成長の促進に必要な“真のコーチング”とは
特別対談収録
須江航(仙台育英硬式野球部監督)
池上正(サッカー指導者)
萩原智子(元日本代表競泳選手)
スポーツ指導における「叱る」について、
その本質や向き合い方をさまざまな角度から掘り下げていく一冊です。
スポーツ界には未だに怒声や暴言、厳しい叱責を含めた「苦痛を用いた指導」が存在し、社会問題になっています。
本書はスポーツライターの大利実氏との共著という形を取っています。私自身は対人支援やコンサルティングの現場からスポーツ指導に関心を持っている人間であり、実際にスポーツ現場で指導してきた専門家ではありません。
そこで、野球界を中心に長年、育成世代の取材を続けている大利氏から、「叱る」についてさまざまな角度から問いを投げかけていただき、それに私が答える形で進めていきます。
指導者自身が「叱る」の根本を知り、理解を深めていくことが、子どもたちの心を育てる指導につながっていくと、私自身は考えています。
------------------
(目次)
第1章 人はなぜ叱りたくなるのか
第2章 叱ることで人の心は育つのか
第3章 スポーツ界に求められる指導法
第4章 指導現場からの質問に答えます
-
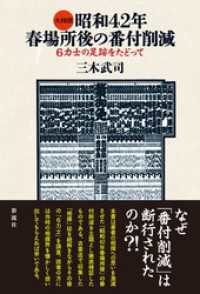
- 電子書籍
- 大相撲昭和42年春場所後の番付削減 6…